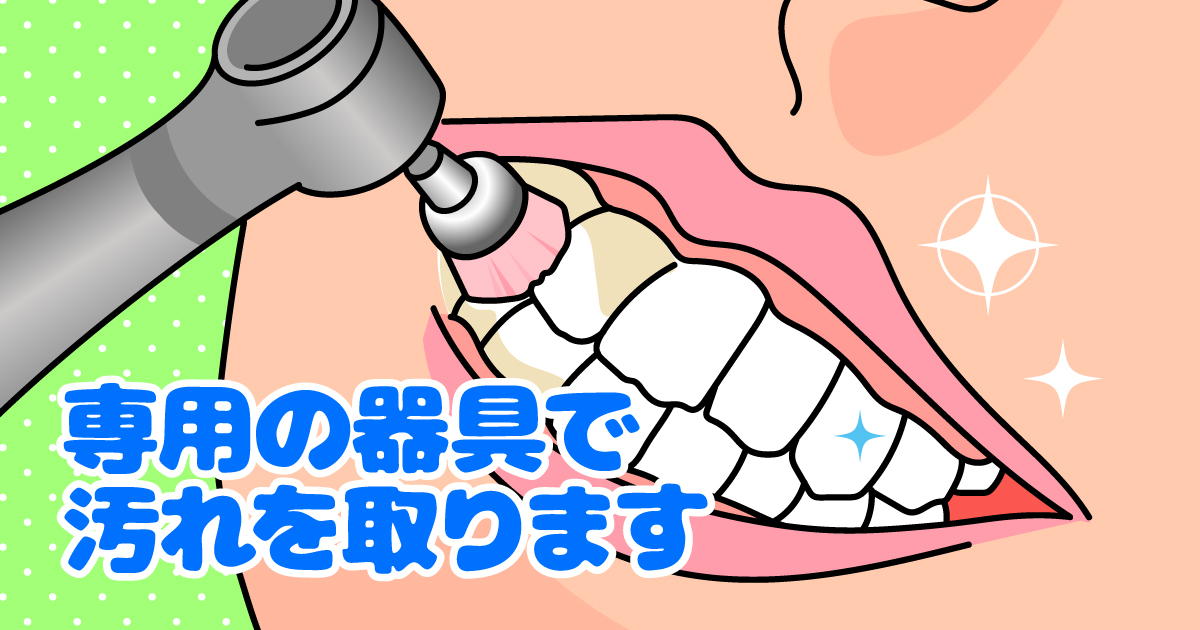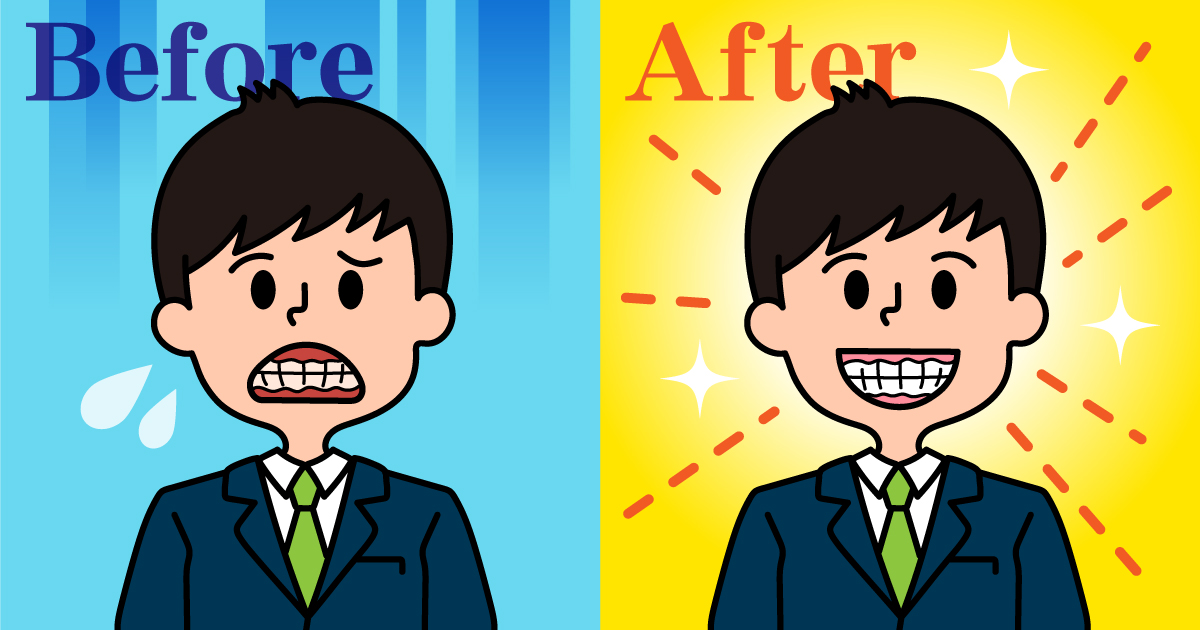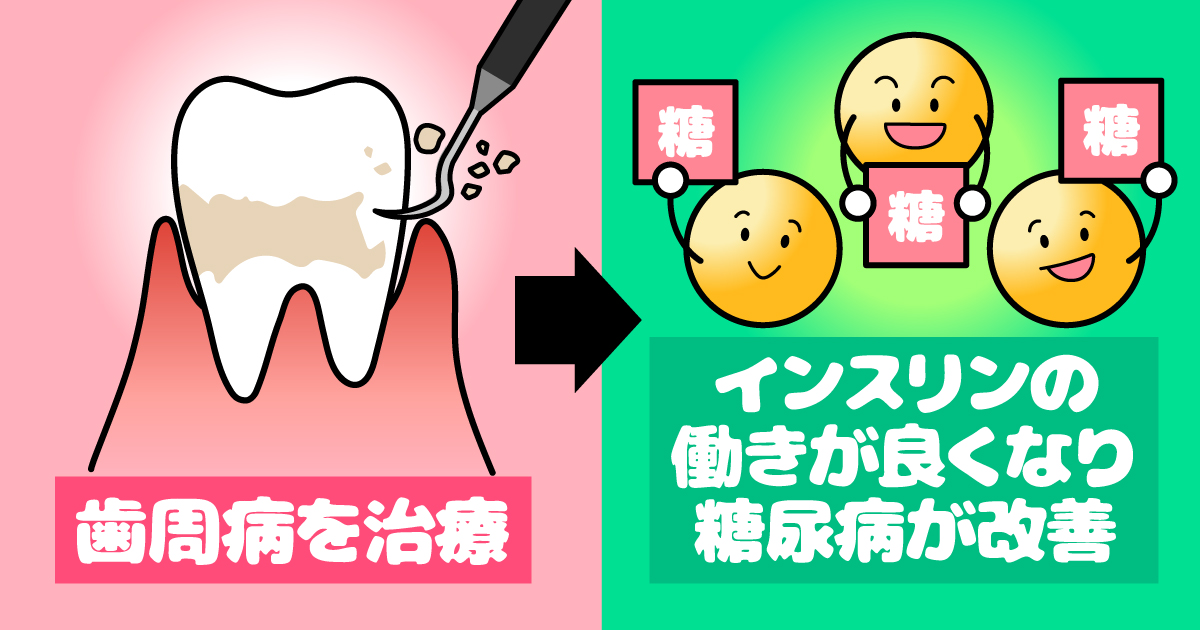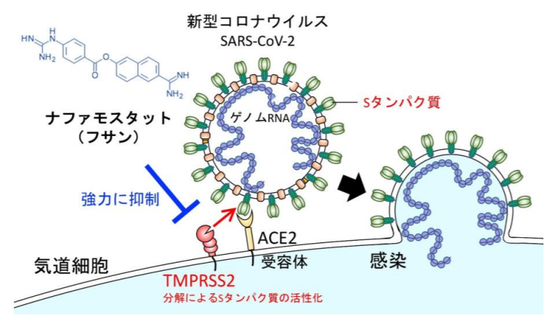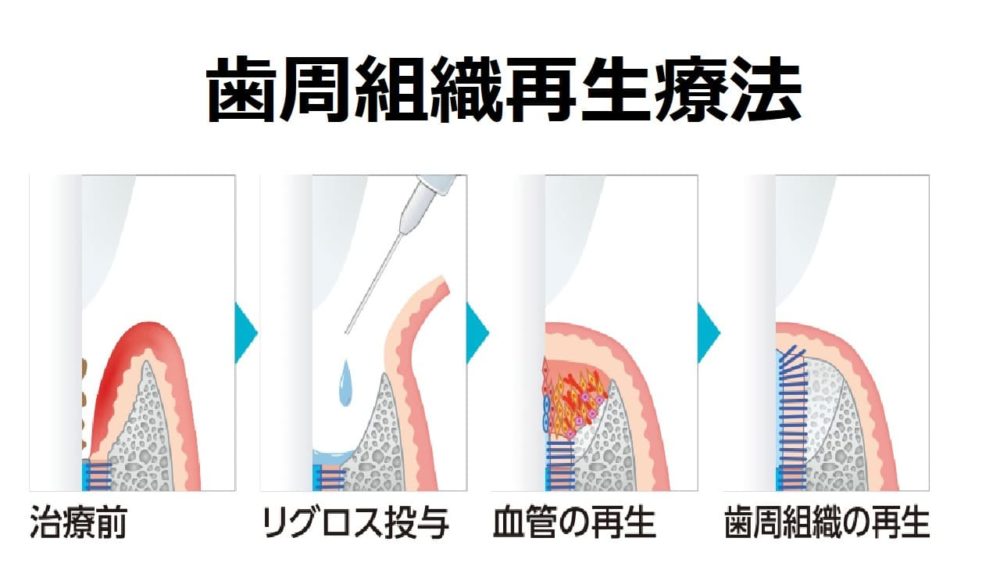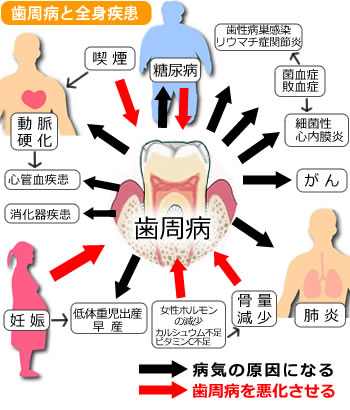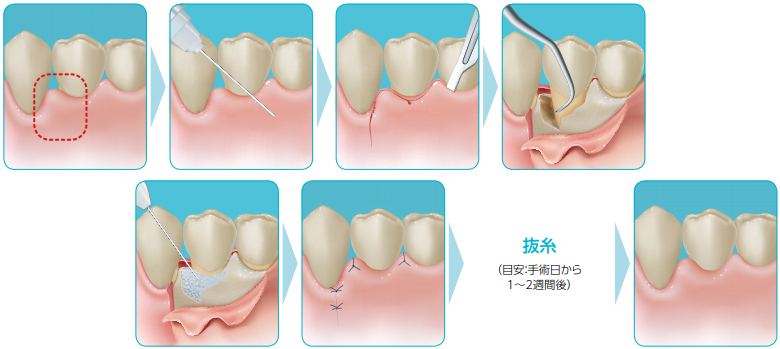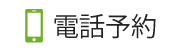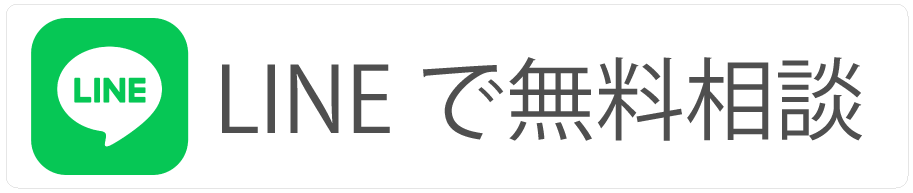こんにちは、院長の葉です。
6月に入り雨模様が続くこの時期は、
なんとなく気分がすぐれない日も
あるかもしれません。
そんな気だるさから、
普段は当たり前に行っている習慣を
疎かにしてしまうと、
健康状態が悪化するリスクを
招くことがあります。
そのリスクのひとつが「歯石」です。
日々の歯みがきが不十分だと
歯に付着した歯垢(プラーク)が
やがて歯石となり、
色々な害を引き起こします。
中には
「歯石を自分で取り除いている」
という人もいるかもしれませんが、
この行為は効果が無く、
むしろ危険を伴うため注意が必要です!
◆毒性があるのは歯石ではなく、
歯石につく◯◯!
歯石とは、
歯の周囲に溜まった
細菌の塊である歯垢(プラーク)が
だ液に含まれるミネラル成分によって
石のように硬くなり、蓄積したものです。
歯石には大きく分けて、
目に見える黄白色の
「歯肉縁上歯石(しにくえんじょうしせき)」と、
歯ぐきの下に隠れている、黒っぽい
「歯肉縁下歯石(しにくえんかしせき)」があります。
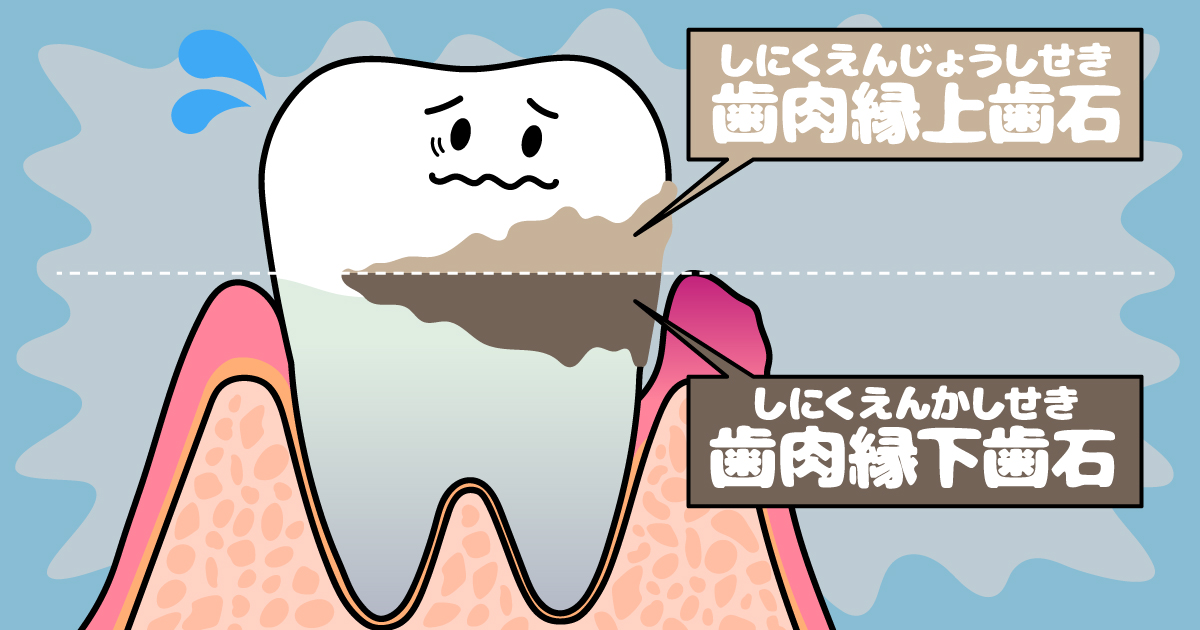
この歯石自体に毒性はありませんが、
お口の健康のためには
取り除くことが必須です。
その理由は、
ざらざらした歯石の表面が
細菌の繁殖にはうってつけの環境であり、
この細菌が、歯や歯ぐきに
悪影響を及ぼしてしまうからです。
◆歯石を放置するとこんなことが…!
細菌だらけの歯石を
除去しないまま放置すると、
やがて歯周病が悪化する
原因となります。
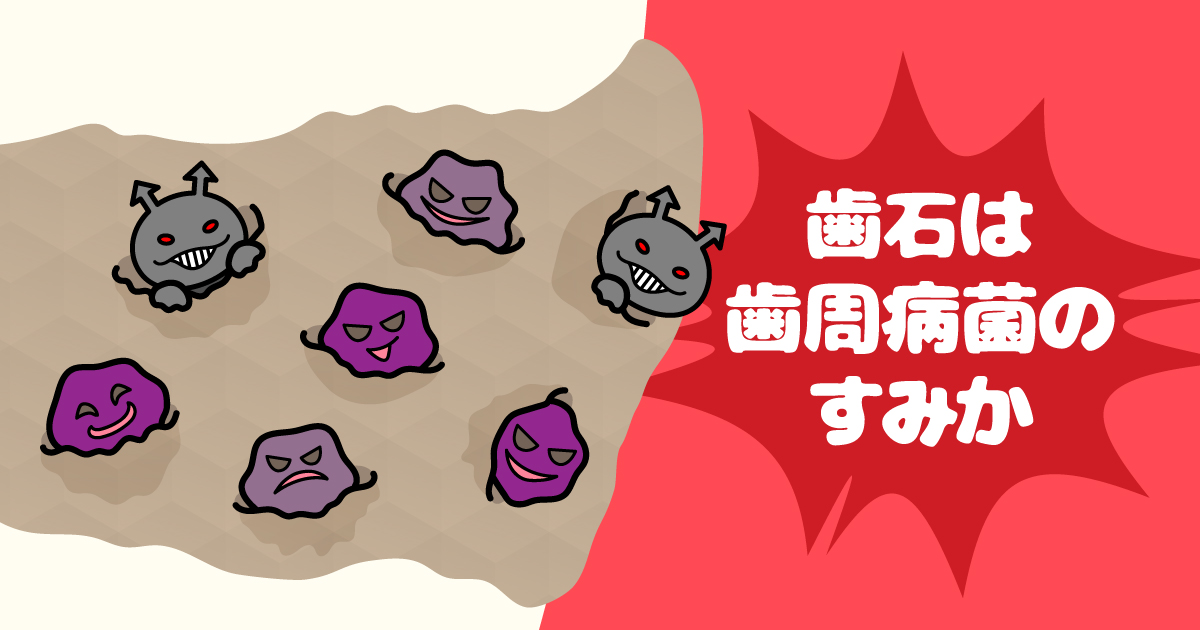
歯石の表面の凹凸に入り込んでいる細菌は、
通常の歯みがきでは完全に除去できません。
その結果、歯石がついた周囲の歯ぐきで
炎症が起こって腫れてしまい、
歯と歯ぐきの間のみぞ(歯周ポケット)が深くなります。
この環境下で歯周病菌が増えることで、
歯周病が悪化していきます。
さらに、歯周病菌は
悪臭を伴うガスを放つため、
口臭も強くなってしまいます。
これらを回避するためには、
細菌のすみかとなる歯石を
早めに取り除くことが肝心です。
◆絶対やめた方がいい…
自分で歯石を取る危険性とは?
歯石を早く取ったほうがいい、となると、
「自分で歯石を取ってしまおう!」
と考える人もいるかもしれません。
しかし、自分で歯石を取ろうとすると
歯や歯ぐきを傷つけることになり、
歯石を全て取ることも不可能です。
また、取り残された歯石に付着した細菌は、
変わらず毒素を出し続けるため、
歯周病や口臭が確実に悪化します。
このように逆効果にしかならないため、
自分で歯石を除去する
メリットはありません。

これらの理由から、
歯石を自分で取ることは絶対に避けましょう。
◆歯石の害、どうしたら食い止められる?
歯石への最善の対処法、
それはズバリ、
「定期的に歯科医院で取ってもらうこと」です。
歯石は一度取った後も、
お口の中のプラークが再び歯石となり、
繰り返し付着してしまいます。
そのため、一般的には
3~6か月に一度のペースで
定期的に歯石取りに通い、
きれいな状態を保つことをおすすめします。
お口の悩みのタネとなる歯石を
歯科医院で安全かつきれいに取り除き、
健康な歯ぐきを維持していきましょう!
医療法人社団 ハートデンタルクリニック
〒885-0031
宮崎県都城市天神町19街区21号
TEL:0986-58-7700
URL:https://heartdental.net/
Googleマップ:https://goo.gl/maps/yw2nLxy4g5DYhZus7