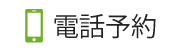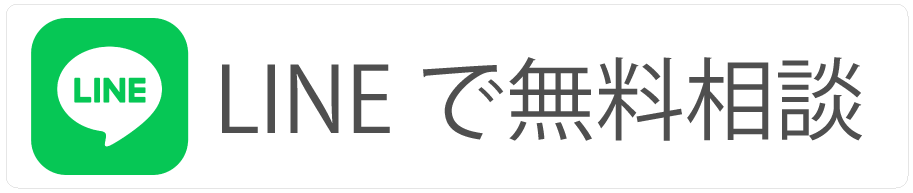子どもの食事時の姿勢は、咀嚼・嚥下機能の発達や顎の成長、歯列の健全な形成に大きく関わります。正しい姿勢を保つことで、食べこぼしや丸のみ、偏った咀嚼といった問題の予防につながります。
まず重要なのは「足が床や足台にしっかりついていること」です。足がぶらぶらしていると体幹が安定せず、姿勢が崩れやすくなり、集中して食べられません。足がつくことで骨盤が立ち、正しい座位を保ちやすくなります。
椅子とテーブルの高さにも注意が必要です。ひじが自然にテーブルにのる高さが理想で、肩が上がったり、身体を前に突き出したりしないよう調整します。背中はまっすぐにし、骨盤が後傾しないようサポートします。背もたれを活用するか、必要であればクッションを使いましょう。
また、顔とお皿の距離は約30cmが目安です。顔を近づけすぎると猫背になりやすく、逆に遠すぎると食具を使いにくくなります。頭を突き出した姿勢は、顎や頸部に余計な負担をかけるため避けましょう。
さらに、肩や首に余計な力が入っていないかも確認してください。緊張していると舌や口唇の運動がスムーズに行えず、正しい咀嚼・嚥下動作が妨げられることがあります。
子どもには「背中ピンとして!」などの抽象的な指示より、「お山の背中だね」や「おひざぺったんこにしようね」など、イメージしやすく優しい声かけが有効です。日々の積み重ねで、良い姿勢と正しい食べ方が自然と身につくようサポートしましょう。
【1〜2歳】姿勢の土台づくりの時期
1〜2歳は、座る・食べる・飲み込むといった動作を覚える大切な時期です。この段階では、体の安定が第一です。足がしっかり床や足台につくように調整することが最も重要です。足がぶらぶらしていると骨盤が後傾し、背中が丸まりやすく、咀嚼や嚥下に影響を及ぼします。
椅子とテーブルの高さも要チェックです。肘が自然にテーブルに乗る高さを基準に、クッションなどで調整しましょう。椅子の座面が広すぎたり滑りやすかったりすると、安定して座れないので、必要に応じて滑り止めやクッションを使うのがよいです。
この年齢では、まだ自分で姿勢を意識するのは難しいため、「おひざぺったんこにしようね」など、具体的でわかりやすい声かけが効果的です。
【3歳】自分で姿勢を意識し始める時期
3歳になると、運動機能や理解力が発達し、自分で食べる意欲も高まります。食具の操作も上手になり、姿勢に対しての声かけも通じやすくなります。この時期のポイントは、「正しい姿勢を習慣化すること」です。
まず、足裏がしっかり台につき、膝が90度になる姿勢を整えることで、体幹の安定と集中力の維持につながります。テーブルの高さは、肘が軽く曲がって自然に乗る位置が目安です。顔をお皿に近づけすぎないよう、顔とお皿の距離は30cm前後を保つようにします。
また、猫背や前のめりになりすぎないよう、食事中に声かけで促します。背筋が曲がってきたら、「背中、お山になってるかな?」などの優しい表現が効果的です。
この時期は、姿勢の乱れが口呼吸・歯列不正・偏咀嚼につながることがあるため、毎日の食事でしっかり観察し、気になる点があれば早めに専門家へ相談することも大切です。
引用参考文献:nico2025年4月




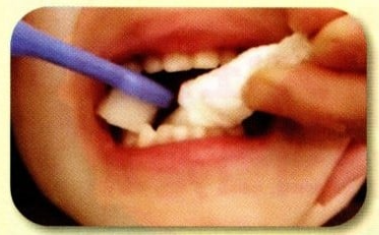

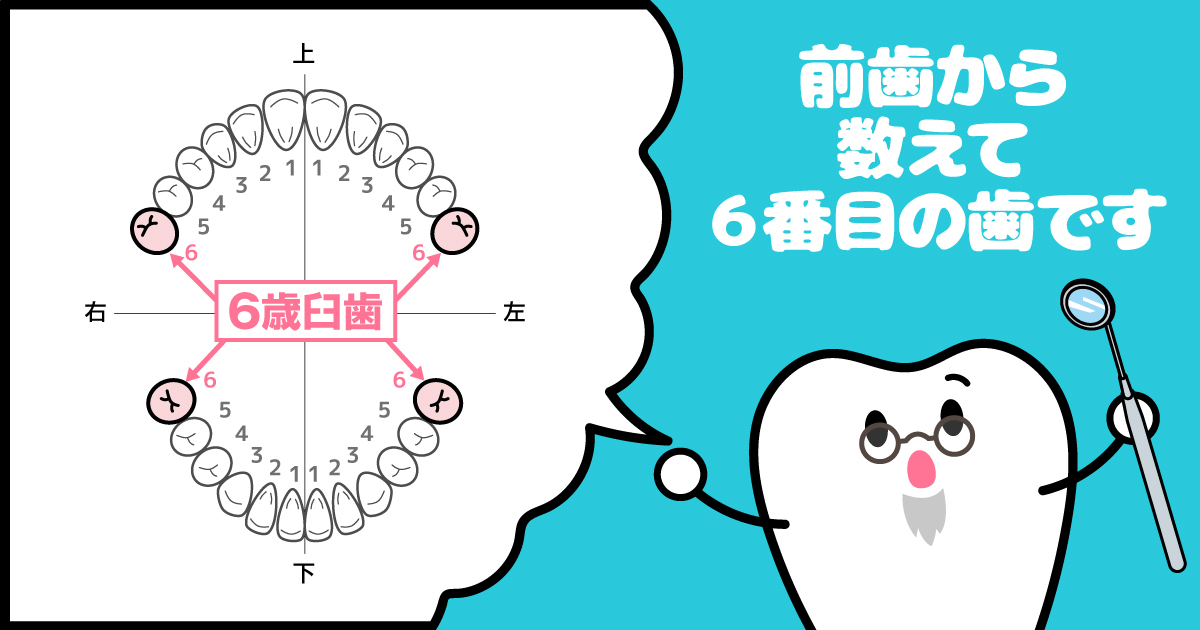
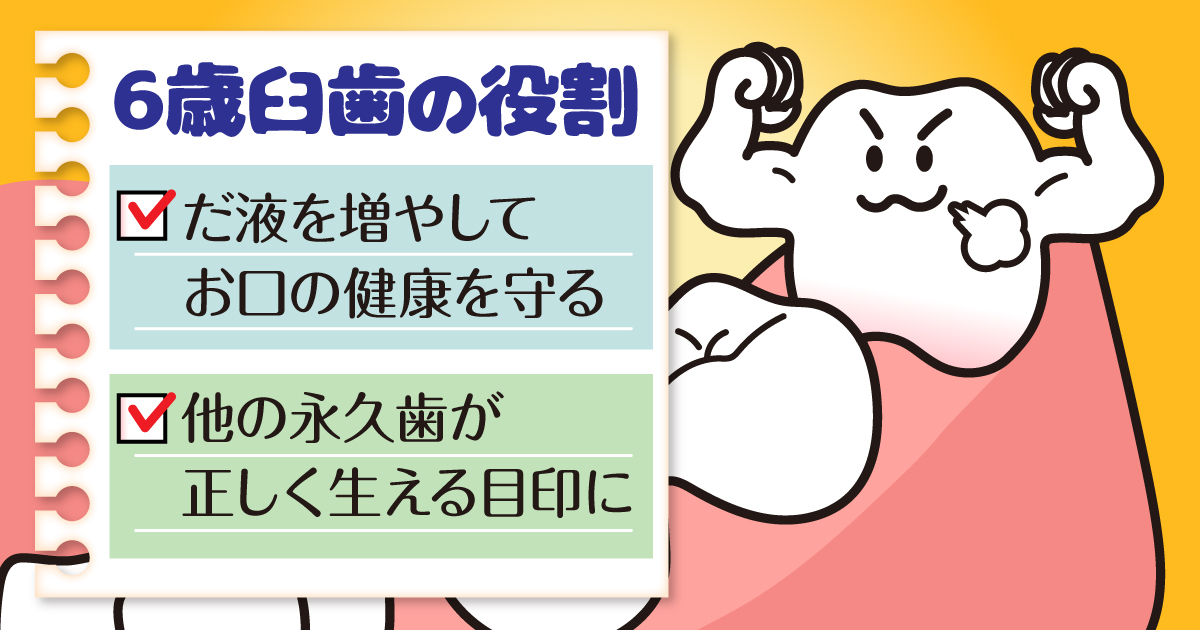
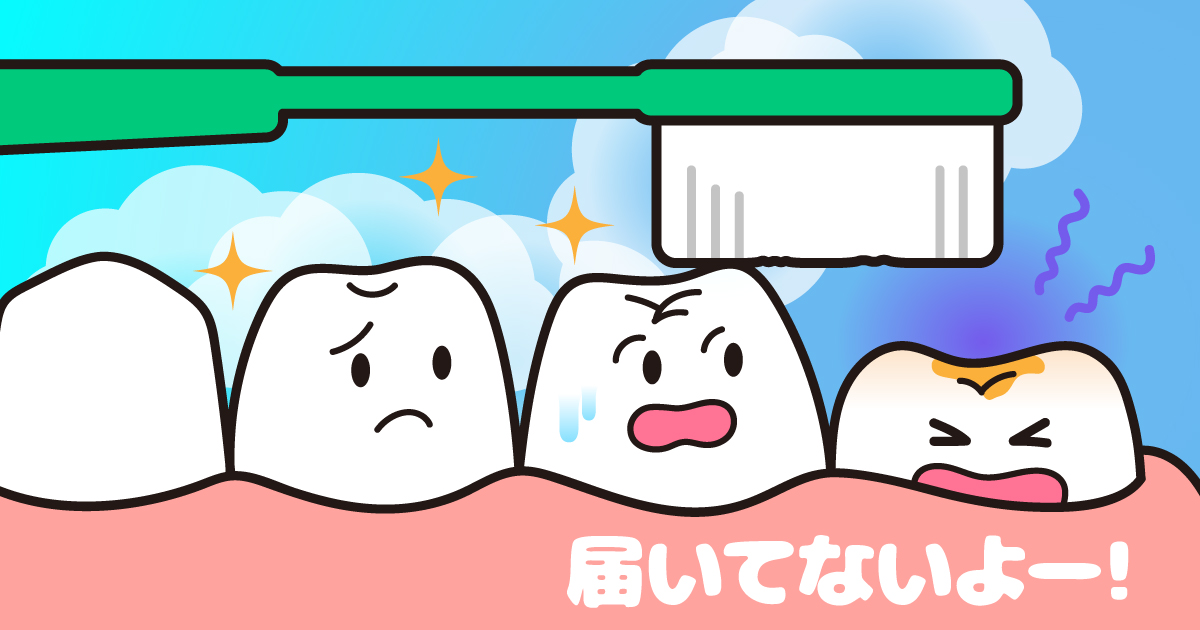







 “
“