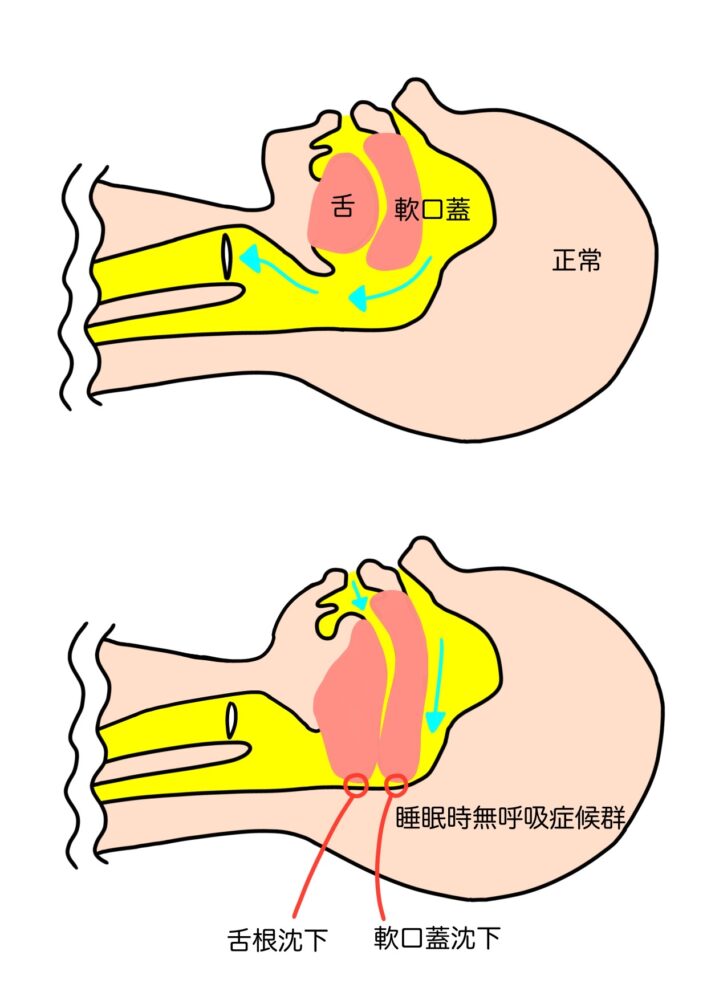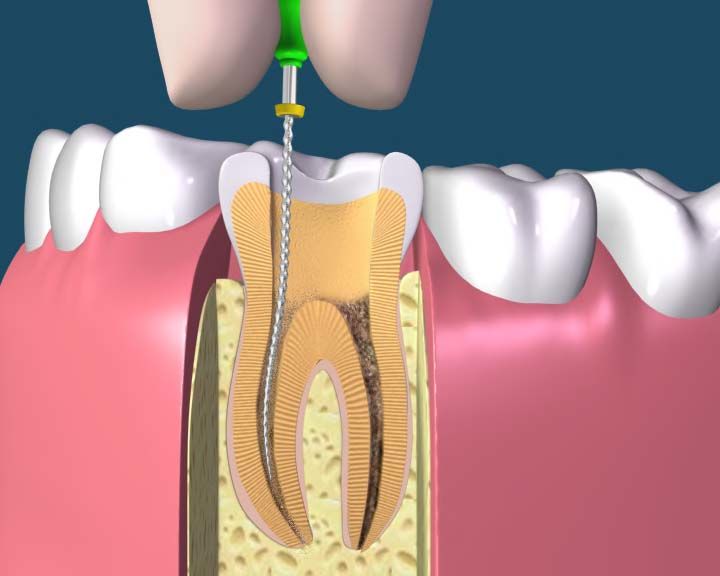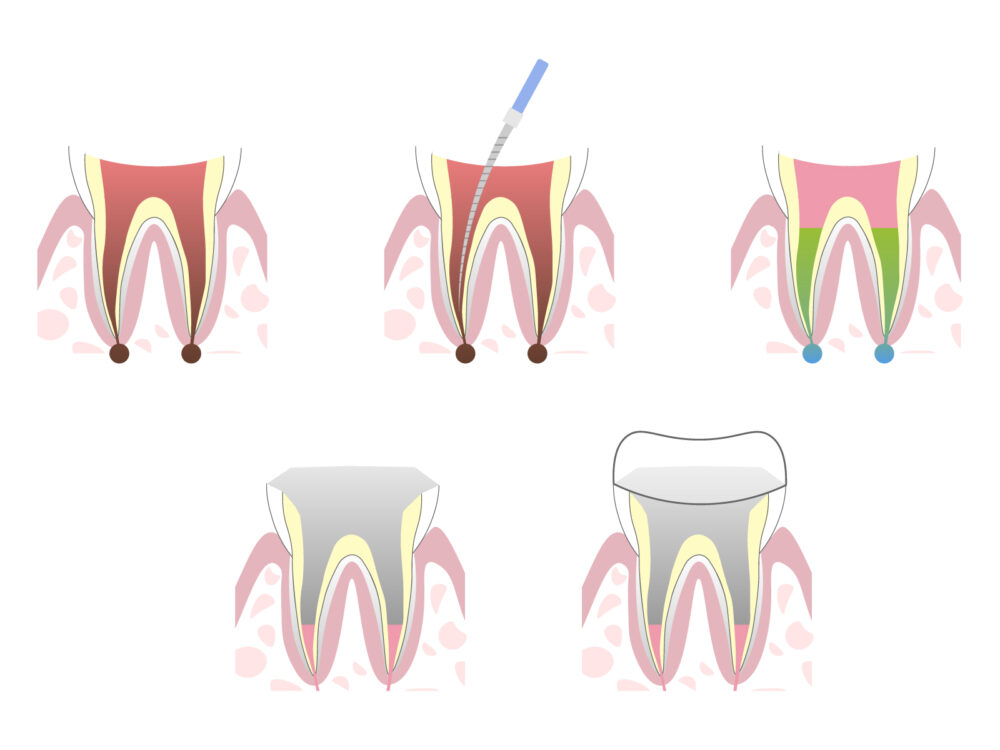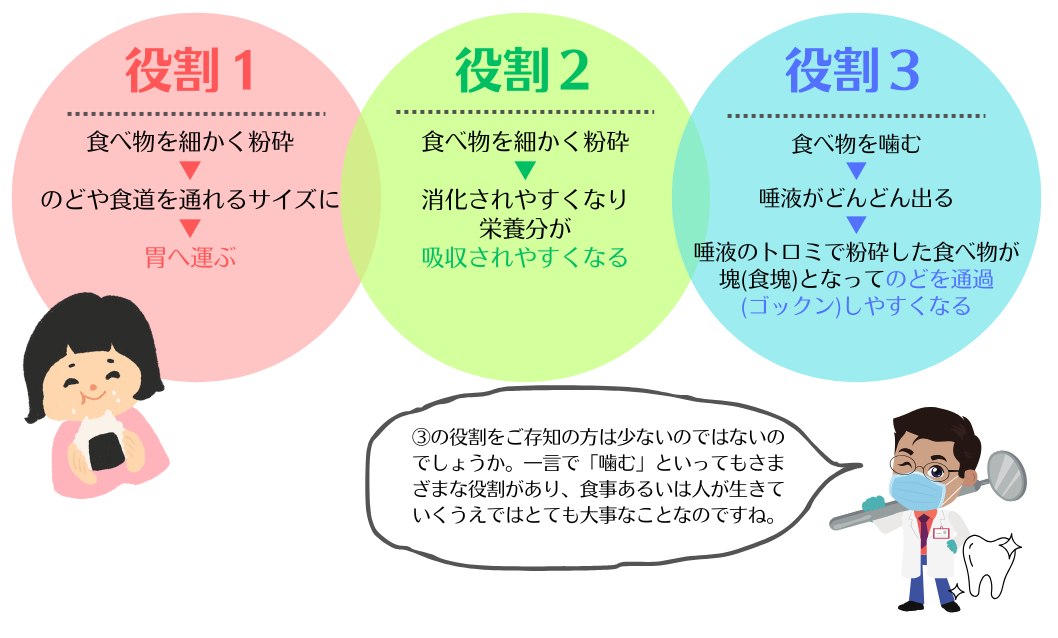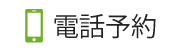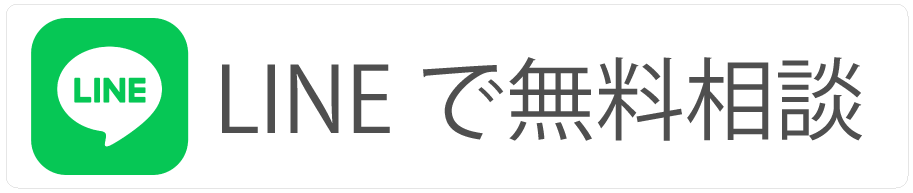皆さんは「口腔機能低下症(こうくうきのうていかしょう)」という言葉を聞いたことがありますか?
少し難しく聞こえますが、簡単にいうと お口の働きが年齢や体調の変化で少しずつ弱っていくこと をいいます。
食べること、話すこと、笑うこと――これらはすべてお口の大切な役割。
その力が弱まると、毎日の生活にも影響が出てしまいます。
こんな症状ありませんか?
✅食べ物を噛みにくくなった
✅飲み込みにくくて、むせやすい
✅発音がはっきりしなくなった
✅口がよく乾く
✅硬い物を避けるようになった
✅食事に時間がかかる
「年のせいかな」と思いがちですが、実はこれが口腔機能低下症のサインかもしれません。
放っておくとどうなるの?
お口の力が弱まると、次のようなことにつながります。
✅栄養がとりにくくなり、体力が落ちる
✅むせやすくなり、誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)のリスクが高まる
✅会話がしにくくなり、人と話すのがおっくうになる
つまり、お口の元気がなくなると 体も心も元気をなくしてしまう 可能性があるのです。
歯科医院でできること
口腔機能低下症は、歯科医院でのチェックで早めに気づくことができます。
検査では、噛む力や飲み込む力、舌や唇の動き、唾液の量などを調べます。
必要に応じて
✅義歯(入れ歯)の調整
✅舌や唇のトレーニング
✅お口のリハビリ なども行います。
ご家庭でできる予防法
お口の機能は、毎日の生活で守ることができます。
✅よく噛む習慣を大切にする(やわらかい物ばかりにしない)
✅舌の運動(舌を回したり、舌を前に出したり)
✅発音トレーニング(「パ・タ・カ・ラ」と声を出す体操)
✅唇をしっかり閉じる運動(口をすぼめる、ブクブクうがい)
✅水分をしっかりとる
これらを続けることで、お口の元気を保ちやすくなります。
まとめ
口腔機能低下症は「歯の病気」ではなく、お口全体の働きが少しずつ弱っていくことです。
「噛みにくい」「飲み込みにくい」などのサインを感じたら、ぜひ早めに歯科で相談してください。
お口の健康は、体の健康、そして毎日の楽しみに直結しています。
歯科医院は お口の“元気”を守るパートナーです。
引用参考文献:nico2025年7月