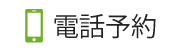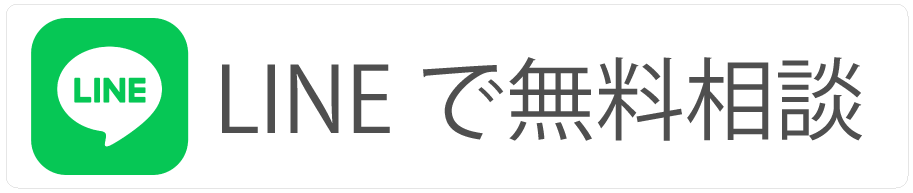最近よくいわれているのが
『 子どもの噛む力の低下 』。。。
この傾向はますます深刻になってきています。
実は、この 『 噛む力をつけていく 』 というのは歯が生えてくる前の段階から関係していて、赤ちゃんの母乳を吸う行為は噛むためのトレーニング期間ということです。
このときに重要なのは “ あごの発育 ”で、噛むときに使う筋肉などは後からでも鍛えられますが、あごが未発達で小さいままだと、乳歯はならぶことができても永久歯がきれいにならぶことが出来なくなるからです。
また、他で問題になっているのが、
『 子どもたちの姿勢の悪さ 』。。。
姿勢の悪さは噛む力にも直接影響してくるので
①. 背筋と首をまっすぐに伸ばした状態と
②. 頭を落として背筋を丸めた状態で
口をパクパクしてみると、明らかに首を伸ばした方が、あごを動かしやすいのが分かると思います。
(高齢になって介護が必要な場合は、基本的に背筋が曲がってきていたりするので、噛みにくかったり、飲み込みにくかったりするといわれています。)
さらに悪い姿勢が習慣化して、あごや噛み合わせがズレたり、それが原因でさらに姿勢がくずれるという悪循環にもなります。
あと興味深いのは、『 あごの発育と生活習慣 』で、確かな傾向としてでているのは、あごの発達した子どもは
“ 身体をよく使い、メリハリのある生活をしている ”
たとえば、早寝早起き・好き嫌いがない・外遊びが好き・がまん強い・食事のときテレビをみない etc.
ということで、出生時からの積み重ねてきた親の成果です。
また、最近の子どもに多いのが 『 だ液の少なさ 』。
これは、その子が緊張状態(ストレス状態)にあることを示しているので、
「 何か心配事があるのかな? 」と考えるサインになります。
この子どもの緊張を解くためには、良い点をたっぷりほめることにあるので、リラックスして感情表現をのびのび出来るようになると驚くほどいろいろな点で成長すると思います。
噛む刺激というのは
理性や思いやり、想像力など
をつかさどる脳の前頭野を発達させるので、食事の時間はゆったりとることを心がけるといいです。
分かっていてもなかなか難しいですが。。。。。
矯正の治療開始年齢
よく質問されるのが、矯正っていつから始めたらいいのでしょうか? というものです。
まず、乳歯の段階では経過を見る場合が多いですが、この段階でも早期治療が必要になるのが、
①.反対咬合(はんたいこうごう)・・・いわゆる受け口の場合
②.顎偏位(がくへんい)・・・上下の真ん中が合わずに顎が左右どちらかにずれているために、奥歯が左右どちらか反対咬合になっている場合
などで、永久歯の交換まで経過をみても、そのままで改善する可能性は10%以下といわれています。
もちろん、①の乳歯の反対咬合などの場合は改善しても、骨格型の場合(原因が顎の成長による場合)などでは、永久歯で再度反対咬合になる可能性もありますが、何もしないで経過をみるよりは、明らかに予後はいいといえます。
また、②の場合などは、経過をみた場合には、極端にいえば左右の顎に成長差ができてしまい、顔付きも左右非対称になる可能性も高くなってしまいます。
この大きく2つ以外では乳歯列の時期(1歳~6歳くらいまで)は経過をみる場合が多いですが、明らかに永久歯の歯がはえてくるスペースがない場合には、お子さんの治療協力度を考えて、早くから歯が生えてくるスペース作りのために
“ 側方拡大床装置 (そくほうかくだいしょうそうち)”
という取り外し式の装置をはめる場合もあります。
( ※ 画像1が上で2が下の装置の1例です。 )
1番大事なのは、乳歯から永久歯へのはえかわり時にチェックするのが最適です。
まずは
『 前歯のはえかわる幼稚園の年長~小学2年生ころ 』
で、このころは乳歯の1番奥から噛み合わせにもとても重要な6歳臼歯の永久歯もはえてきます。
この時期に上下4本ずつの前歯がきちんとスペースにはまっていれば、
(あとから交換する乳歯の3本分のスペースと永久歯の3本分のスペースではわずかながら乳歯の方が大きい場合が多いので)
問題なく永久歯への交換がスムーズにいく可能性が高くなります。
いいかえると、この時期のうちに問題を少しずつでも改善できると、永久臼歯(えいきゅうしのおくば)がすべてはえそろってからの処置が最小限で済むため、負担も軽くなります。
ここが通常での矯正の治療開始時期の最適期
なので、少しでも気になる点などがありましたら、この時期までに一度相談してみるのがいいと思います。
次にチェックするのは
『 犬歯~奥歯がはえかわる小学4年~中学1年のころ 』
で、ここで6歳臼歯のさらに奥から最後の奥歯がはえてきて、永久歯列の完成になります。
ここで、前歯がはえかわる時に部分矯正をしたお子さんなども最終的に歯の整列が必要かの最終判断をしていきます。
これ以降は歯のはえかわりなどもないため、極端にいえば大人になってから治療するのとあまり変わらない処置が必要になる場合(永久歯の抜歯など)が多いです。
つまり矯正の場合、早い時期であれば永久歯を抜歯しないですむという選択肢もあるのですが、年齢を重ねるだけ治療の選択肢が抜歯してからの処置しかないetc.だいぶ限定されてしまいます。
そのためにも、お子さんの定期健診ではむし歯だけでなく、噛み合わせの経過をみるために、はえかわりなどがない時期は6ヶ月ごとくらいですが、はえかわりの時期では3~4ヵ月ごとの定期健診受診をおすすめしています。
もちろん個人差も大きいですので、分からないことなどは遠慮されずにご質問下さい^^
まだまだ、書き足りないですが。。。
 “
“
まず、乳歯の段階では経過を見る場合が多いですが、この段階でも早期治療が必要になるのが、
①.反対咬合(はんたいこうごう)・・・いわゆる受け口の場合
②.顎偏位(がくへんい)・・・上下の真ん中が合わずに顎が左右どちらかにずれているために、奥歯が左右どちらか反対咬合になっている場合
などで、永久歯の交換まで経過をみても、そのままで改善する可能性は10%以下といわれています。
もちろん、①の乳歯の反対咬合などの場合は改善しても、骨格型の場合(原因が顎の成長による場合)などでは、永久歯で再度反対咬合になる可能性もありますが、何もしないで経過をみるよりは、明らかに予後はいいといえます。
また、②の場合などは、経過をみた場合には、極端にいえば左右の顎に成長差ができてしまい、顔付きも左右非対称になる可能性も高くなってしまいます。
この大きく2つ以外では乳歯列の時期(1歳~6歳くらいまで)は経過をみる場合が多いですが、明らかに永久歯の歯がはえてくるスペースがない場合には、お子さんの治療協力度を考えて、早くから歯が生えてくるスペース作りのために
“ 側方拡大床装置 (そくほうかくだいしょうそうち)”
という取り外し式の装置をはめる場合もあります。
( ※ 画像1が上で2が下の装置の1例です。 )
1番大事なのは、乳歯から永久歯へのはえかわり時にチェックするのが最適です。
まずは
『 前歯のはえかわる幼稚園の年長~小学2年生ころ 』
で、このころは乳歯の1番奥から噛み合わせにもとても重要な6歳臼歯の永久歯もはえてきます。
この時期に上下4本ずつの前歯がきちんとスペースにはまっていれば、
(あとから交換する乳歯の3本分のスペースと永久歯の3本分のスペースではわずかながら乳歯の方が大きい場合が多いので)
問題なく永久歯への交換がスムーズにいく可能性が高くなります。
いいかえると、この時期のうちに問題を少しずつでも改善できると、永久臼歯(えいきゅうしのおくば)がすべてはえそろってからの処置が最小限で済むため、負担も軽くなります。
ここが通常での矯正の治療開始時期の最適期
なので、少しでも気になる点などがありましたら、この時期までに一度相談してみるのがいいと思います。
次にチェックするのは
『 犬歯~奥歯がはえかわる小学4年~中学1年のころ 』
で、ここで6歳臼歯のさらに奥から最後の奥歯がはえてきて、永久歯列の完成になります。
ここで、前歯がはえかわる時に部分矯正をしたお子さんなども最終的に歯の整列が必要かの最終判断をしていきます。
これ以降は歯のはえかわりなどもないため、極端にいえば大人になってから治療するのとあまり変わらない処置が必要になる場合(永久歯の抜歯など)が多いです。
つまり矯正の場合、早い時期であれば永久歯を抜歯しないですむという選択肢もあるのですが、年齢を重ねるだけ治療の選択肢が抜歯してからの処置しかないetc.だいぶ限定されてしまいます。
そのためにも、お子さんの定期健診ではむし歯だけでなく、噛み合わせの経過をみるために、はえかわりなどがない時期は6ヶ月ごとくらいですが、はえかわりの時期では3~4ヵ月ごとの定期健診受診をおすすめしています。
もちろん個人差も大きいですので、分からないことなどは遠慮されずにご質問下さい^^
まだまだ、書き足りないですが。。。

 “
“ 歯磨きを嫌がる時は?
小さいお子さんがお家などで、歯磨きをさせてくれないんですよ~という言葉をよくお聞きします。
これにはやはり理由があり、大きく分けて5つあります。
1つ目は、子供が歯を磨かれることに慣れていないため、口の中を触られるのがイヤ!という場合で、
①.最初は指で触ってから、歯ブラシで触るなどしてだんだんと慣らしていくことが必要です。
②.上の前歯が1番敏感で嫌がる場合が多いので、磨く順番を
下の奥歯⇒上の奥歯⇒下の前歯⇒上の前歯のように嫌がらない順番でしていくなどの工夫も必要です。
2つ目は、お母さんの歯磨きが痛いのでイヤ!という場合で、
この場合はお母さんの歯磨きテクニックを向上する必要がありますが、特に左手の人差し指をうまく使うのが重要です。
例えば、
上の前歯を磨くときには上唇小帯(じょうしんしょうたい)という上唇の裏のスジを引っ掛けないように人差し指でガードしたり、
奥歯を磨くときには、大きくお口を開けると逆に磨きずらいので、少しお口を閉じてもらってから人差し指をほっぺたの裏に入れてほっぺたを軽く引っ張ると、痛くなく奥まで歯ブラシが届きやすく、磨きやすくなります。
3つ目は、母親が子供の歯を磨くことに慣れていないのでイヤ!という場合で、
お母さんが心に余裕がないときに無理やり磨こうとして怖がられるような時です。このような時は、お母さん自身がリラックスするために唄を歌ってあげたり、話しかけたりしながら磨くといいです。
4つ目は、子供の機嫌が悪いときにむりやり磨こうとするのでイヤ!という場合で、
①.子供の機嫌がいい時や、眠くなる前に磨いたり、
②.機嫌の悪いときには、この時期1番むし歯になりやすい上の前歯だけを磨いてあげたりする
などの工夫が必要です。
5つ目は、歯磨き剤がイヤ!という場合で、
もちろん、2歳くらいまで(ブクブクうがいができるようになるくらいまで)は無理に使う必要はなく、歯磨き自体が大切なので、しっかり磨き残しをなくすようにすることが必要です。
それ以降も無理にしようする必要はないですが、フッ素入りのものなどもうまく取り入れていくといいと思います。
分からないことなどは、ドンドンご質問下さい^^
これにはやはり理由があり、大きく分けて5つあります。
1つ目は、子供が歯を磨かれることに慣れていないため、口の中を触られるのがイヤ!という場合で、
①.最初は指で触ってから、歯ブラシで触るなどしてだんだんと慣らしていくことが必要です。
②.上の前歯が1番敏感で嫌がる場合が多いので、磨く順番を
下の奥歯⇒上の奥歯⇒下の前歯⇒上の前歯のように嫌がらない順番でしていくなどの工夫も必要です。
2つ目は、お母さんの歯磨きが痛いのでイヤ!という場合で、
この場合はお母さんの歯磨きテクニックを向上する必要がありますが、特に左手の人差し指をうまく使うのが重要です。
例えば、
上の前歯を磨くときには上唇小帯(じょうしんしょうたい)という上唇の裏のスジを引っ掛けないように人差し指でガードしたり、
奥歯を磨くときには、大きくお口を開けると逆に磨きずらいので、少しお口を閉じてもらってから人差し指をほっぺたの裏に入れてほっぺたを軽く引っ張ると、痛くなく奥まで歯ブラシが届きやすく、磨きやすくなります。
3つ目は、母親が子供の歯を磨くことに慣れていないのでイヤ!という場合で、
お母さんが心に余裕がないときに無理やり磨こうとして怖がられるような時です。このような時は、お母さん自身がリラックスするために唄を歌ってあげたり、話しかけたりしながら磨くといいです。
4つ目は、子供の機嫌が悪いときにむりやり磨こうとするのでイヤ!という場合で、
①.子供の機嫌がいい時や、眠くなる前に磨いたり、
②.機嫌の悪いときには、この時期1番むし歯になりやすい上の前歯だけを磨いてあげたりする
などの工夫が必要です。
5つ目は、歯磨き剤がイヤ!という場合で、
もちろん、2歳くらいまで(ブクブクうがいができるようになるくらいまで)は無理に使う必要はなく、歯磨き自体が大切なので、しっかり磨き残しをなくすようにすることが必要です。
それ以降も無理にしようする必要はないですが、フッ素入りのものなどもうまく取り入れていくといいと思います。
分からないことなどは、ドンドンご質問下さい^^
感染の窓とは???
先日、あった
鹿児島大学歯学部の宮崎在住のOBの北辰会
の講演会で、2期卒業で岐阜市開業の 稲葉 幸二 先生のお話しがあり、
先生ご自身の子育ての経験もふまえながらの講演で、
『 むし歯ゼロの子育て法~感染の窓をいかに開けないか 』
という題目でした。
この題目だけでも、予防を中心に考えている自分としては、とても興味があり、土曜日午後の診療を少し早めに切り上げて行ってきたのですが、とても身になるお話しでした。
まとめてみると、
『感染の窓』 といわれる時期である
赤ちゃんが誕生して19ヶ月~31ヶ月の間
にその子の口腔常在細菌叢(こうくうじょうざいさいきんそう・・・お口の中に常にいる細菌の種類の割合)が決定すると言われているので、この時期にむし歯の原因菌である
S.mutans(ミュータンス菌)やS.sobrinus(ソブリヌス菌)
に感染してお口の中に定着してしまうとむし歯の危険性がとても高くなる、というものです。
(この時期の前までは母乳などが守ってくれるのですが…)
逆に、この時期をクリアー(つまり、3歳くらいまでにお菓子やジュースなどの砂糖を与えなければ)すれば、
“ むし歯予防は簡単にできる ”
というものです。3歳までに甘いものを与えなければ、その後の味覚形成や食習慣(甘いものを欲しがらない、偏食しないetc.)にも影響するので、食育でもここが1番大事な時期なのかなあ。。。と強く感じました。
この『 感染の窓 』の時期の予防法としては
(1)「感染を防ぐ」ためには
・・・母親のミュータンス菌のレベルを低くするために母親のブラッシングが重要
(2)「定着を防ぐ」ためには
・・・感染が起こってもミュータンス菌の住みにくい環境を作るために食生活指導(甘味制限)が重要
ただ、『 むし歯になる4つの条件 』というものがあり、これはあくまでも糖質に対するアプローチにすぎません。
4つの条件とは
①むし歯菌(口の中には約3億の細菌が住んでいます。その中でミュータンス菌がプラークの原因となります)
⇒ 正しいブラッシングによるむし歯菌の減少
②糖質(食べ物の中の糖分をミュータンス菌が分解して、ネバネバしたデキストランを作り、これが歯にこびりつきます)
⇒ 砂糖の制限(代替甘味料の摂取・・・キシリトールなど)
③歯の質(歯の形や歯ならび、そして歯が作られる期間の栄養や病気などが、むし歯に強い歯や弱い歯を作ります)
⇒ フッ素塗布、フッ素洗口、ミネラルパックetc.
④時間(歯に糖質が接触する回数、時間が増えるとむし歯になります)
⇒ おやつを与える回数や時間を決める
(種類についてもおやつ=お菓子ではなく、おにぎり・季節の野菜・果物なども不足がちな栄養の補給という点ではいいと思います)
上記の4つの条件が重なってむし歯になると言われていますので、1つだけを実行しても充分な予防にはならないということも考えていくといいと思います。
他にも面白いデータなどもあったのですが、長くなったのでまた次回以降で。。。
P.S. 稲葉先生が書いた絵本
『 どーしてわたしにはムシバがないの 』
もキッズルームの歯に関するたくさんの絵本の中にありますので、興味ある方は見てみてください^^
 “
“
鹿児島大学歯学部の宮崎在住のOBの北辰会
の講演会で、2期卒業で岐阜市開業の 稲葉 幸二 先生のお話しがあり、
先生ご自身の子育ての経験もふまえながらの講演で、
『 むし歯ゼロの子育て法~感染の窓をいかに開けないか 』
という題目でした。
この題目だけでも、予防を中心に考えている自分としては、とても興味があり、土曜日午後の診療を少し早めに切り上げて行ってきたのですが、とても身になるお話しでした。
まとめてみると、
『感染の窓』 といわれる時期である
赤ちゃんが誕生して19ヶ月~31ヶ月の間
にその子の口腔常在細菌叢(こうくうじょうざいさいきんそう・・・お口の中に常にいる細菌の種類の割合)が決定すると言われているので、この時期にむし歯の原因菌である
S.mutans(ミュータンス菌)やS.sobrinus(ソブリヌス菌)
に感染してお口の中に定着してしまうとむし歯の危険性がとても高くなる、というものです。
(この時期の前までは母乳などが守ってくれるのですが…)
逆に、この時期をクリアー(つまり、3歳くらいまでにお菓子やジュースなどの砂糖を与えなければ)すれば、
“ むし歯予防は簡単にできる ”
というものです。3歳までに甘いものを与えなければ、その後の味覚形成や食習慣(甘いものを欲しがらない、偏食しないetc.)にも影響するので、食育でもここが1番大事な時期なのかなあ。。。と強く感じました。
この『 感染の窓 』の時期の予防法としては
(1)「感染を防ぐ」ためには
・・・母親のミュータンス菌のレベルを低くするために母親のブラッシングが重要
(2)「定着を防ぐ」ためには
・・・感染が起こってもミュータンス菌の住みにくい環境を作るために食生活指導(甘味制限)が重要
ただ、『 むし歯になる4つの条件 』というものがあり、これはあくまでも糖質に対するアプローチにすぎません。
4つの条件とは
①むし歯菌(口の中には約3億の細菌が住んでいます。その中でミュータンス菌がプラークの原因となります)
⇒ 正しいブラッシングによるむし歯菌の減少
②糖質(食べ物の中の糖分をミュータンス菌が分解して、ネバネバしたデキストランを作り、これが歯にこびりつきます)
⇒ 砂糖の制限(代替甘味料の摂取・・・キシリトールなど)
③歯の質(歯の形や歯ならび、そして歯が作られる期間の栄養や病気などが、むし歯に強い歯や弱い歯を作ります)
⇒ フッ素塗布、フッ素洗口、ミネラルパックetc.
④時間(歯に糖質が接触する回数、時間が増えるとむし歯になります)
⇒ おやつを与える回数や時間を決める
(種類についてもおやつ=お菓子ではなく、おにぎり・季節の野菜・果物なども不足がちな栄養の補給という点ではいいと思います)
上記の4つの条件が重なってむし歯になると言われていますので、1つだけを実行しても充分な予防にはならないということも考えていくといいと思います。
他にも面白いデータなどもあったのですが、長くなったのでまた次回以降で。。。
P.S. 稲葉先生が書いた絵本
『 どーしてわたしにはムシバがないの 』
もキッズルームの歯に関するたくさんの絵本の中にありますので、興味ある方は見てみてください^^
 “
“