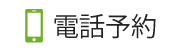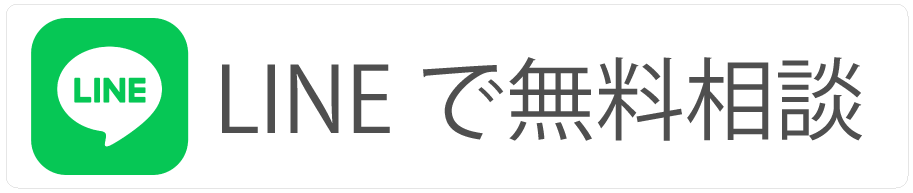日本での糖尿病患者数は900万人弱(2007年の国民栄養調査)といわれていますが糖尿病の可能性が否定できない人も加えると2210万人と想定されているそうです。
原因は主に生活習慣の欧米化といわれていますが、糖尿病が怖いのは網膜症、腎症、心疾患などのさまざまな合併症を一緒に引き起こすところで、歯周病もその一つとして挙げられています。(最近はTV番組でも2時間スペシャルを組んでまで歯周病の特集をしていましたのでご存知の方も多いと思いますが。。。)
この歯周病を放っておくと、糖尿病患者はインスリンの効きが悪くなって糖尿病が悪化し、歯周病もさらにひどくなる可能性があります。
逆に血糖値の管理をし、歯周病の治療をした患者の場合は、歯の状態もだんだんよくなり、歯周病治療をすることによりインスリンが働きやすい状態になるため、血糖コントロールが改善する事例も報告されているとのことです。
これまでも書いたことがありますが、歯周病はさらに心筋梗塞や脳梗塞などの心臓血管疾患を発症するリスクも2.2~3.4倍になることも報告されていて、歯周病がひどくなると細菌などが歯ぐきの血管内に入って体中を駆け巡り、心臓や脳の血管に達して心筋梗塞や脳梗塞のような血管の病気を引き起こすことがあるのです。
歯周病を防ぐことは、糖尿病の悪化を抑え、心筋梗塞などの予防、ひいては全身の健康にもつながるのです。
(他にも歯周病と関連のある疾患としては低体重児出産、呼吸器系疾患、消化器系疾患、骨粗しょう症など様々です)
また30歳代以上の8割以上が歯周病といわれていて、ほとんど自覚症状がないので早期発見して治療することが大事です。
(一度失われたアゴの骨や歯ぐきは元にもどりません)
さらに歯周病になって治療が終わった人と、一度もなっていない人では、経験した人の方が再発しやすいため、かかりつけの歯科を決めて定期的に歯の健康の維持・管理を行うことがおススメです。
それ以上に歯みがきや歯間ブラシなどでのオーラルケアを毎日しっかり行うことで歯周病は予防できるので、セルフケアでの自己管理が大切です。
ちなみに11月14日は「世界糖尿病デー」で、2006年の国連総会で指定されました。
(このときに 『糖尿病の全世界的脅威を認知する決議』 も同時に採択されるほどになっています)
また自分も 「日本糖尿病協会」 にも属していて、歯科医師からの歯周病と糖尿病(もしくは全身疾患)との関連の情報をできるだけ多くの方々に発信できるようにしています。
※今回のブログは日本歯科医師会広報の『歯っぴいスマイル』を参考に記載しています
歯周病とからだ①
歯周病は最近はテレビなどでもよく扱われるようになってきたので以前よりは身近に詳しい方も多くなってきたようですが。
今回は、その中でも女性のからだについて少し書きます。。。
まず妊娠した場合ですが、妊娠中はつわりなどでブラッシングがむずかしくなりやすかったり、ホルモンバランスが崩れたりで、歯ぐきの炎症がおこり歯周病になる人が多くなります。
さらに妊婦さんが歯周病になると、おなかの赤ちゃんが小さく生まれたり、早産となるリスクが高くなったりすることが知られています。
これは歯周病の炎症で出てくる
“ プロスタグランジン ”(子宮収縮などに関わる生理活性物質)
などの物質が、胎盤に影響を与えるためだと考えられています。
なので、妊娠中は自分のためだけでなく、生まれてくる赤ちゃんのためにも、お口の状態に気をつけましょう!^^
特に安定期の5~7ヶ月はほとんどの処置が問題なく受けられる場合が多いですが、もし麻酔の使用やレントゲン撮影などで不安なことがあれば担当の婦人科の先生にご相談するのもいいと思います。(歯周病の処置の歯石除去などはほぼ問題ないです)
次に骨粗しょう症(骨密度が減ってスカスカになり骨折しやすくなる病気で女性に多く、閉経後の女性ホルモンの低下が主な原因といわれています)の方が歯周病になると、歯槽骨(しそうこつ)という歯を支える骨が急速にやせてしまいます。
そうなると入れ歯(部分入れ歯、総入れ歯ともに)を使用している方は、それらが合わなくなったりします。
また歯周病で歯を失うと、噛む力が衰えることにより食事によって得られるカルシウムも不足することになり、さらに骨を弱くしてしまうという悪循環も招いてしまいます。
これ以外にも歯周病は全身のいろんな病気と深く関わっていますので、少しずつ書き込んでいきます。。。
今回は、その中でも女性のからだについて少し書きます。。。
まず妊娠した場合ですが、妊娠中はつわりなどでブラッシングがむずかしくなりやすかったり、ホルモンバランスが崩れたりで、歯ぐきの炎症がおこり歯周病になる人が多くなります。
さらに妊婦さんが歯周病になると、おなかの赤ちゃんが小さく生まれたり、早産となるリスクが高くなったりすることが知られています。
これは歯周病の炎症で出てくる
“ プロスタグランジン ”(子宮収縮などに関わる生理活性物質)
などの物質が、胎盤に影響を与えるためだと考えられています。
なので、妊娠中は自分のためだけでなく、生まれてくる赤ちゃんのためにも、お口の状態に気をつけましょう!^^
特に安定期の5~7ヶ月はほとんどの処置が問題なく受けられる場合が多いですが、もし麻酔の使用やレントゲン撮影などで不安なことがあれば担当の婦人科の先生にご相談するのもいいと思います。(歯周病の処置の歯石除去などはほぼ問題ないです)
次に骨粗しょう症(骨密度が減ってスカスカになり骨折しやすくなる病気で女性に多く、閉経後の女性ホルモンの低下が主な原因といわれています)の方が歯周病になると、歯槽骨(しそうこつ)という歯を支える骨が急速にやせてしまいます。
そうなると入れ歯(部分入れ歯、総入れ歯ともに)を使用している方は、それらが合わなくなったりします。
また歯周病で歯を失うと、噛む力が衰えることにより食事によって得られるカルシウムも不足することになり、さらに骨を弱くしてしまうという悪循環も招いてしまいます。
これ以外にも歯周病は全身のいろんな病気と深く関わっていますので、少しずつ書き込んでいきます。。。
治療した歯が痛~いのはなぜ?
ときどき、この前治療したばっかりの歯が痛くなることってありませんか?
その歯は治療する前も、冷たい物がしみたり、噛むと痛かったりはなかったでしょうか?
患者さまの立場だと、むし歯を治療してもらったのに痛くなるのはおかしい。。。ということになると思います。
ごもっともです。
ただ、これはどういうことかというと治療する前から自覚症状があるということは、むし歯が深かったということを現しています。
そこで、もちろんむし歯になっていたやわらかい歯の質(軟化象牙質・なんかぞうげしつ)を染め出しながら、慎重に取り除いていきます。
で、こういう場合は、神経などの入っている歯髄(しずい)の近くまで到達していることが多いのです。
ここからの処置では
Ⅰ.歯髄までむし歯が達している場合
これは、このまま詰めたりしても、すぐに痛みが出る可能性が高いので、抜髄(ばつずい)といって神経を除去する処置をして、何回か根管内を清掃して感染しない状態までになったら、詰めたり、被せたりしていきます。
Ⅱ.歯髄まではむし歯がだいぶ近いが、達していない場合
①.あとから痛みがでる可能性が高いので、ここで抜髄処置まで行う場合。
②.あとから痛みがでる可能性は高いが、できるだけ歯髄を残すように覆とう(ふくとう)・裏装(りそう)といって歯髄を保護する材料を二重に置いてから詰めたり、被せたりする場合。
の2つの方法です。
患者さまからすれば、痛みがでる可能性があるならば、歯髄(神経など)は抜いちゃえ!(もっと極端な場合は、痛い原因の歯を抜いちゃえ!)って考えると思います。
ただ、この歯髄には神経だけでなく血管などもあるので、この抜髄(ばつずい)という処置を行うと、死んだ組織として歯はそこにとどまり続けるのです。(体の中では死んだ組織として残るのは“ 歯 ”だけです。)
もちろん、歯の寿命は短くなりますし、前歯などでは歯の色も変わってきます。(のちのち後悔する場合が殆どです)
なので、歯医者としては、できるだけ歯の神経は残すようになんとか努力するのです。
そうすると、場合によっては詰め物などをしてしばらくは大丈夫でも1ヶ月くらいしてからしみたり、痛みがでたりすることもあります。
そうすると冒頭の
“ 治療した歯が痛~いのはなぜ? ”
となるのです。
もちろん、抜髄の処置自体はそんなに大変な処置ではないのですが、患者さまの長い一生のことを考えると、
「 できるだけ神経を抜かない、歯を抜かない 」
という当たり前のことが大事になってきます。
自分の考え方としては、
「 小さいむし歯は削らずに定期健診で経過観察していく 」
ということです。(自分の歯に勝るものなし!)
なので、よく聞くのが
“ 説明なく削られた、神経を抜かれた、歯を抜かれた ”
ということが今も往々にしてよくあるということです。
処置で少しでも
“ ん ? ”
っと疑問に思ったら、質問するのは患者さまの権利です。
そこは
百聞は一見にしかず
ではないですが、削った歯は元には戻らないので、早めにきくのは大事です。
ちなみに自分の1番の考えは
「 後戻りできる(可逆的な)処置を優先して行う 」
というものです。歯が痛いと患者さまが訴えても、そこに十分な原因を自分が診断できなければ、その日は噛み合わせの状態を確認するために歯型だけとってそれで終了の場合もあります。
患者さまとしては、痛いと言ってるのに何もしてくれない、と考えると思いますが、風邪の引きはじめや疲れていたりで、体の抵抗力が落ちている場合だけ症状がでたり、原因が歯ではなくて関連痛だったりすることも多いもので。。。
まずは、はっきりした原因を特定できなければ、積極的な処置(削ったりなど。。。)は決して行いません!
こういう考えのもとで治療を行っていますので、ご質問などはご遠慮なくどうぞ!^^
その歯は治療する前も、冷たい物がしみたり、噛むと痛かったりはなかったでしょうか?
患者さまの立場だと、むし歯を治療してもらったのに痛くなるのはおかしい。。。ということになると思います。
ごもっともです。
ただ、これはどういうことかというと治療する前から自覚症状があるということは、むし歯が深かったということを現しています。
そこで、もちろんむし歯になっていたやわらかい歯の質(軟化象牙質・なんかぞうげしつ)を染め出しながら、慎重に取り除いていきます。
で、こういう場合は、神経などの入っている歯髄(しずい)の近くまで到達していることが多いのです。
ここからの処置では
Ⅰ.歯髄までむし歯が達している場合
これは、このまま詰めたりしても、すぐに痛みが出る可能性が高いので、抜髄(ばつずい)といって神経を除去する処置をして、何回か根管内を清掃して感染しない状態までになったら、詰めたり、被せたりしていきます。
Ⅱ.歯髄まではむし歯がだいぶ近いが、達していない場合
①.あとから痛みがでる可能性が高いので、ここで抜髄処置まで行う場合。
②.あとから痛みがでる可能性は高いが、できるだけ歯髄を残すように覆とう(ふくとう)・裏装(りそう)といって歯髄を保護する材料を二重に置いてから詰めたり、被せたりする場合。
の2つの方法です。
患者さまからすれば、痛みがでる可能性があるならば、歯髄(神経など)は抜いちゃえ!(もっと極端な場合は、痛い原因の歯を抜いちゃえ!)って考えると思います。
ただ、この歯髄には神経だけでなく血管などもあるので、この抜髄(ばつずい)という処置を行うと、死んだ組織として歯はそこにとどまり続けるのです。(体の中では死んだ組織として残るのは“ 歯 ”だけです。)
もちろん、歯の寿命は短くなりますし、前歯などでは歯の色も変わってきます。(のちのち後悔する場合が殆どです)
なので、歯医者としては、できるだけ歯の神経は残すようになんとか努力するのです。
そうすると、場合によっては詰め物などをしてしばらくは大丈夫でも1ヶ月くらいしてからしみたり、痛みがでたりすることもあります。
そうすると冒頭の
“ 治療した歯が痛~いのはなぜ? ”
となるのです。
もちろん、抜髄の処置自体はそんなに大変な処置ではないのですが、患者さまの長い一生のことを考えると、
「 できるだけ神経を抜かない、歯を抜かない 」
という当たり前のことが大事になってきます。
自分の考え方としては、
「 小さいむし歯は削らずに定期健診で経過観察していく 」
ということです。(自分の歯に勝るものなし!)
なので、よく聞くのが
“ 説明なく削られた、神経を抜かれた、歯を抜かれた ”
ということが今も往々にしてよくあるということです。
処置で少しでも
“ ん ? ”
っと疑問に思ったら、質問するのは患者さまの権利です。
そこは
百聞は一見にしかず
ではないですが、削った歯は元には戻らないので、早めにきくのは大事です。
ちなみに自分の1番の考えは
「 後戻りできる(可逆的な)処置を優先して行う 」
というものです。歯が痛いと患者さまが訴えても、そこに十分な原因を自分が診断できなければ、その日は噛み合わせの状態を確認するために歯型だけとってそれで終了の場合もあります。
患者さまとしては、痛いと言ってるのに何もしてくれない、と考えると思いますが、風邪の引きはじめや疲れていたりで、体の抵抗力が落ちている場合だけ症状がでたり、原因が歯ではなくて関連痛だったりすることも多いもので。。。
まずは、はっきりした原因を特定できなければ、積極的な処置(削ったりなど。。。)は決して行いません!
こういう考えのもとで治療を行っていますので、ご質問などはご遠慮なくどうぞ!^^
治療した歯が痛~いのはなぜ?
ときどき、この前治療したばっかりの歯が痛くなることってありませんか?
その歯は治療する前も、冷たい物がしみたり、噛むと痛かったりはなかったでしょうか?
患者さまの立場だと、むし歯を治療してもらったのに痛くなるのはおかしい。。。ということになると思います。
ごもっともです。
ただ、これはどういうことかというと治療する前から自覚症状があるということは、むし歯が深かったということを現しています。
そこで、もちろんむし歯になっていたやわらかい歯の質(軟化象牙質・なんかぞうげしつ)を染め出しながら、慎重に取り除いていきます。
で、こういう場合は、神経などの入っている歯髄(しずい)の近くまで到達していることが多いのです。
ここからの処置では
Ⅰ.歯髄までむし歯が達している場合
これは、このまま詰めたりしても、すぐに痛みが出る可能性が高いので、抜髄(ばつずい)といって神経を除去する処置をして、何回か根管内を清掃して感染しない状態までになったら、詰めたり、被せたりしていきます。
Ⅱ.歯髄まではむし歯がだいぶ近いが、達していない場合
①.あとから痛みがでる可能性が高いので、ここで抜髄処置まで行う場合。
②.あとから痛みがでる可能性は高いが、できるだけ歯髄を残すように覆とう(ふくとう)・裏装(りそう)といって歯髄を保護する材料を二重に置いてから詰めたり、被せたりする場合。
の2つの方法です。
患者さまからすれば、痛みがでる可能性があるならば、歯髄(神経など)は抜いちゃえ!(もっと極端な場合は、痛い原因の歯を抜いちゃえ!)って考えると思います。
ただ、この歯髄には神経だけでなく血管などもあるので、この抜髄(ばつずい)という処置を行うと、死んだ組織として歯はそこにとどまり続けるのです。(体の中では死んだ組織として残るのは“ 歯 ”だけです。)
もちろん、歯の寿命は短くなりますし、前歯などでは歯の色も変わってきます。(のちのち後悔する場合が殆どです)
なので、歯医者としては、できるだけ歯の神経は残すようになんとか努力するのです。
そうすると、場合によっては詰め物などをしてしばらくは大丈夫でも1ヶ月くらいしてからしみたり、痛みがでたりすることもあります。
そうすると冒頭の
“ 治療した歯が痛~いのはなぜ? ”
となるのです。
もちろん、抜髄の処置自体はそんなに大変な処置ではないのですが、患者さまの長い一生のことを考えると、
「 できるだけ神経を抜かない、歯を抜かない 」
という当たり前のことが大事になってきます。
自分の考え方としては、
「 小さいむし歯は削らずに定期健診で経過観察していく 」
ということです。(自分の歯に勝るものなし!)
なので、よく聞くのが
“ 説明なく削られた、神経を抜かれた、歯を抜かれた ”
ということが今も往々にしてよくあるということです。
処置で少しでも
“ ん ? ”
っと疑問に思ったら、質問するのは患者さまの権利です。
そこは
百聞は一見にしかず
ではないですが、削った歯は元には戻らないので、早めにきくのは大事です。
ちなみに自分の1番の考えは
「 後戻りできる(可逆的な)処置を優先して行う 」
というものです。歯が痛いと患者さまが訴えても、そこに十分な原因を自分が診断できなければ、その日は噛み合わせの状態を確認するために歯型だけとってそれで終了の場合もあります。
患者さまとしては、痛いと言ってるのに何もしてくれない、と考えると思いますが、風邪の引きはじめや疲れていたりで、体の抵抗力が落ちている場合だけ症状がでたり、原因が歯ではなくて関連痛だったりすることも多いもので。。。
まずは、はっきりした原因を特定できなければ、積極的な処置(削ったりなど。。。)は決して行いません!
こういう考えのもとで治療を行っていますので、ご質問などはご遠慮なくどうぞ!^^
その歯は治療する前も、冷たい物がしみたり、噛むと痛かったりはなかったでしょうか?
患者さまの立場だと、むし歯を治療してもらったのに痛くなるのはおかしい。。。ということになると思います。
ごもっともです。
ただ、これはどういうことかというと治療する前から自覚症状があるということは、むし歯が深かったということを現しています。
そこで、もちろんむし歯になっていたやわらかい歯の質(軟化象牙質・なんかぞうげしつ)を染め出しながら、慎重に取り除いていきます。
で、こういう場合は、神経などの入っている歯髄(しずい)の近くまで到達していることが多いのです。
ここからの処置では
Ⅰ.歯髄までむし歯が達している場合
これは、このまま詰めたりしても、すぐに痛みが出る可能性が高いので、抜髄(ばつずい)といって神経を除去する処置をして、何回か根管内を清掃して感染しない状態までになったら、詰めたり、被せたりしていきます。
Ⅱ.歯髄まではむし歯がだいぶ近いが、達していない場合
①.あとから痛みがでる可能性が高いので、ここで抜髄処置まで行う場合。
②.あとから痛みがでる可能性は高いが、できるだけ歯髄を残すように覆とう(ふくとう)・裏装(りそう)といって歯髄を保護する材料を二重に置いてから詰めたり、被せたりする場合。
の2つの方法です。
患者さまからすれば、痛みがでる可能性があるならば、歯髄(神経など)は抜いちゃえ!(もっと極端な場合は、痛い原因の歯を抜いちゃえ!)って考えると思います。
ただ、この歯髄には神経だけでなく血管などもあるので、この抜髄(ばつずい)という処置を行うと、死んだ組織として歯はそこにとどまり続けるのです。(体の中では死んだ組織として残るのは“ 歯 ”だけです。)
もちろん、歯の寿命は短くなりますし、前歯などでは歯の色も変わってきます。(のちのち後悔する場合が殆どです)
なので、歯医者としては、できるだけ歯の神経は残すようになんとか努力するのです。
そうすると、場合によっては詰め物などをしてしばらくは大丈夫でも1ヶ月くらいしてからしみたり、痛みがでたりすることもあります。
そうすると冒頭の
“ 治療した歯が痛~いのはなぜ? ”
となるのです。
もちろん、抜髄の処置自体はそんなに大変な処置ではないのですが、患者さまの長い一生のことを考えると、
「 できるだけ神経を抜かない、歯を抜かない 」
という当たり前のことが大事になってきます。
自分の考え方としては、
「 小さいむし歯は削らずに定期健診で経過観察していく 」
ということです。(自分の歯に勝るものなし!)
なので、よく聞くのが
“ 説明なく削られた、神経を抜かれた、歯を抜かれた ”
ということが今も往々にしてよくあるということです。
処置で少しでも
“ ん ? ”
っと疑問に思ったら、質問するのは患者さまの権利です。
そこは
百聞は一見にしかず
ではないですが、削った歯は元には戻らないので、早めにきくのは大事です。
ちなみに自分の1番の考えは
「 後戻りできる(可逆的な)処置を優先して行う 」
というものです。歯が痛いと患者さまが訴えても、そこに十分な原因を自分が診断できなければ、その日は噛み合わせの状態を確認するために歯型だけとってそれで終了の場合もあります。
患者さまとしては、痛いと言ってるのに何もしてくれない、と考えると思いますが、風邪の引きはじめや疲れていたりで、体の抵抗力が落ちている場合だけ症状がでたり、原因が歯ではなくて関連痛だったりすることも多いもので。。。
まずは、はっきりした原因を特定できなければ、積極的な処置(削ったりなど。。。)は決して行いません!
こういう考えのもとで治療を行っていますので、ご質問などはご遠慮なくどうぞ!^^
歯を抜いてからのブリッジって?
大切な歯をいろいろな理由で抜歯しないといけなくなったときに、その後の補い方として
1.ブリッジ
2.部分床義歯(ぶぶんしょうぎし、小さい入れ歯)
3.インプラント
のどれがいいのか?という説明が歯科医院であると思います。
1.2.は健康保険の範囲内での処置、3.は自費での処置と
費用からは大きく2つに分かれます。
今回はこの中の “ ブリッジ ”について書きます。
ブリッジとは、失った歯の隣りの歯を土台にして、被せものとダミーの歯を連結して作ってある補綴物(ほてつぶつ)をかぶせてガッチリと固定する治療法です。
ちょうど、橋脚に支えられて架かっている橋と同じような構造なので、 “ ブリッジ(橋) ”とよばれています。
この橋脚の役割をしている歯を 「 支台歯(しだいし) 」とよんでいますが、患者さまの歯を削った土台部分で、噛む力を受け止めて連結したクラウンとダミーを支えるという、大変重要な役割を果たしています。
この支台歯が歯周病になって動いてしまうと、噛む力に耐える十分な強度がなくなります。
失ってしまった歯の役割を補っておいしく食べる機能を果たすには、ブリッジがお口の中でグラグラしてしまっては困ります。
なかでも奥歯には、数十キログラムにも及ぶ力がかかりますので、耐久性抜きにはブリッジ治療はできません。
そこで、
①.失った歯の種類(生えていた場所)
②.歯を失った原因
③.これまでの治療経過
④.失った歯とその周りの状況
⑤.患者さまの希望
などをもとにして、より良い予後のために総合的に診査・診断を行います。
ブリッジの支台歯は、たとえば今まで3本の歯で受け止めていた力を真ん中の歯が失われることによって、2本の“ 支台歯 ”が分担して支えていかなければならないのです。
「 ブリッジの治療 」というと、ついクラウン(被せもの)やダミー部の形や色など、いわゆる “ うわもの ”に目がいってしまいますが、実際はそれらを支える縁の下の力持ちの存在の “ 支台歯 ”がもっとも重要なのです。
「 ブリッジはどれくらいもちますか? 」
という質問がよくありますが、快適に長くお使いいただくためには、“ 支台歯 ” の健康がカギとなります。
つまり、治療した(削った)歯は、健康な歯よりもむし歯に再度なったりする危険度もアップします。なので、今まで以上のお手入れが重要になるのはいうまでもありません。
こたえは、 「 お手入れ次第 」 なのです。
また被せていたりすると、外は被せものの形が変化しないので、自分だけでは、中の状況が分かりにくくなります。
歯科医院での定期的な健診を受けることにより、間違いなく、詰めものや被せものは、長く持つようになるということはいえます。
1.ブリッジ
2.部分床義歯(ぶぶんしょうぎし、小さい入れ歯)
3.インプラント
のどれがいいのか?という説明が歯科医院であると思います。
1.2.は健康保険の範囲内での処置、3.は自費での処置と
費用からは大きく2つに分かれます。
今回はこの中の “ ブリッジ ”について書きます。
ブリッジとは、失った歯の隣りの歯を土台にして、被せものとダミーの歯を連結して作ってある補綴物(ほてつぶつ)をかぶせてガッチリと固定する治療法です。
ちょうど、橋脚に支えられて架かっている橋と同じような構造なので、 “ ブリッジ(橋) ”とよばれています。
この橋脚の役割をしている歯を 「 支台歯(しだいし) 」とよんでいますが、患者さまの歯を削った土台部分で、噛む力を受け止めて連結したクラウンとダミーを支えるという、大変重要な役割を果たしています。
この支台歯が歯周病になって動いてしまうと、噛む力に耐える十分な強度がなくなります。
失ってしまった歯の役割を補っておいしく食べる機能を果たすには、ブリッジがお口の中でグラグラしてしまっては困ります。
なかでも奥歯には、数十キログラムにも及ぶ力がかかりますので、耐久性抜きにはブリッジ治療はできません。
そこで、
①.失った歯の種類(生えていた場所)
②.歯を失った原因
③.これまでの治療経過
④.失った歯とその周りの状況
⑤.患者さまの希望
などをもとにして、より良い予後のために総合的に診査・診断を行います。
ブリッジの支台歯は、たとえば今まで3本の歯で受け止めていた力を真ん中の歯が失われることによって、2本の“ 支台歯 ”が分担して支えていかなければならないのです。
「 ブリッジの治療 」というと、ついクラウン(被せもの)やダミー部の形や色など、いわゆる “ うわもの ”に目がいってしまいますが、実際はそれらを支える縁の下の力持ちの存在の “ 支台歯 ”がもっとも重要なのです。
「 ブリッジはどれくらいもちますか? 」
という質問がよくありますが、快適に長くお使いいただくためには、“ 支台歯 ” の健康がカギとなります。
つまり、治療した(削った)歯は、健康な歯よりもむし歯に再度なったりする危険度もアップします。なので、今まで以上のお手入れが重要になるのはいうまでもありません。
こたえは、 「 お手入れ次第 」 なのです。
また被せていたりすると、外は被せものの形が変化しないので、自分だけでは、中の状況が分かりにくくなります。
歯科医院での定期的な健診を受けることにより、間違いなく、詰めものや被せものは、長く持つようになるということはいえます。
詰め物・被せ物が入らないときは。。。
歯医者さんで、この前型を採ったので
“ 今日は詰め物や被せ物が入る日 ”
っていう場合に、歯医者さんで予定と違う場合(今日はセットしてくれなかった)ってあると思います。
この場合に患者さまの立場としてはどう考えるのでしょうか?
まず、原因としてはいろいろなことが考えられます。
1.歯型を採るときのエラー
2.石こうという模型をつくる材料を歯型に流すときのエラー
3.模型上で詰め物、被せ物を製作するときのエラー
などで入らない場合などです。このエラーが調整の範囲内であれば、セット時に入る場合がほとんどです。
ただ、やはりわずかな頻度で、このままセットすると詰め物や被せ物とのすき間が大きくなり、2次的にむし歯になりやすくなることが考えられる場合は、当医院では現状を説明します。
“ 模型上ではこのようにピッタリなのですが、お口の中で合わせると、ほんの少しのすき間ですが、2次的にむし歯になる可能性がありますので、申し訳ないですが、再度型を採って仮のふたをして、次回セットしていきます ”
・・・と。
ただ、この場合でも患者さまは
ここは下手なんだ~
と感じられる方もいらっしゃると思います。
それは確かにエラーがあり、患者さまにご迷惑がかかっているのですが、患者さまのことを考えてのこの現状での最善の処置として行っています。
少しのすき間くらいならセットしてしまえば分からないからいいか、という考えが自分として最も嫌なことなので。。。
少しでも自分の考えが伝わっていただけるとありがたいです。
“ 今日は詰め物や被せ物が入る日 ”
っていう場合に、歯医者さんで予定と違う場合(今日はセットしてくれなかった)ってあると思います。
この場合に患者さまの立場としてはどう考えるのでしょうか?
まず、原因としてはいろいろなことが考えられます。
1.歯型を採るときのエラー
2.石こうという模型をつくる材料を歯型に流すときのエラー
3.模型上で詰め物、被せ物を製作するときのエラー
などで入らない場合などです。このエラーが調整の範囲内であれば、セット時に入る場合がほとんどです。
ただ、やはりわずかな頻度で、このままセットすると詰め物や被せ物とのすき間が大きくなり、2次的にむし歯になりやすくなることが考えられる場合は、当医院では現状を説明します。
“ 模型上ではこのようにピッタリなのですが、お口の中で合わせると、ほんの少しのすき間ですが、2次的にむし歯になる可能性がありますので、申し訳ないですが、再度型を採って仮のふたをして、次回セットしていきます ”
・・・と。
ただ、この場合でも患者さまは
ここは下手なんだ~
と感じられる方もいらっしゃると思います。
それは確かにエラーがあり、患者さまにご迷惑がかかっているのですが、患者さまのことを考えてのこの現状での最善の処置として行っています。
少しのすき間くらいならセットしてしまえば分からないからいいか、という考えが自分として最も嫌なことなので。。。
少しでも自分の考えが伝わっていただけるとありがたいです。
詰め物・被せ物が入らないときは。。。
歯医者さんで、この前型を採ったので
“ 今日は詰め物や被せ物が入る日 ”
っていう場合に、歯医者さんで予定と違う場合(今日はセットしてくれなかった)ってあると思います。
この場合に患者さまの立場としてはどう考えるのでしょうか?
まず、原因としてはいろいろなことが考えられます。
1.歯型を採るときのエラー
2.石こうという模型をつくる材料を歯型に流すときのエラー
3.模型上で詰め物、被せ物を製作するときのエラー
などで入らない場合などです。このエラーが調整の範囲内であれば、セット時に入る場合がほとんどです。
ただ、やはりわずかな頻度で、このままセットすると詰め物や被せ物とのすき間が大きくなり、2次的にむし歯になりやすくなることが考えられる場合は、当医院では現状を説明します。
“ 模型上ではこのようにピッタリなのですが、お口の中で合わせると、ほんの少しのすき間ですが、2次的にむし歯になる可能性がありますので、申し訳ないですが、再度型を採って仮のふたをして、次回セットしていきます ”
・・・と。
ただ、この場合でも患者さまは
ここは下手なんだ~
と感じられる方もいらっしゃると思います。
それは確かにエラーがあり、患者さまにご迷惑がかかっているのですが、患者さまのことを考えてのこの現状での最善の処置として行っています。
少しのすき間くらいならセットしてしまえば分からないからいいか、という考えが自分として最も嫌なことなので。。。
少しでも自分の考えが伝わっていただけるとありがたいです。
“ 今日は詰め物や被せ物が入る日 ”
っていう場合に、歯医者さんで予定と違う場合(今日はセットしてくれなかった)ってあると思います。
この場合に患者さまの立場としてはどう考えるのでしょうか?
まず、原因としてはいろいろなことが考えられます。
1.歯型を採るときのエラー
2.石こうという模型をつくる材料を歯型に流すときのエラー
3.模型上で詰め物、被せ物を製作するときのエラー
などで入らない場合などです。このエラーが調整の範囲内であれば、セット時に入る場合がほとんどです。
ただ、やはりわずかな頻度で、このままセットすると詰め物や被せ物とのすき間が大きくなり、2次的にむし歯になりやすくなることが考えられる場合は、当医院では現状を説明します。
“ 模型上ではこのようにピッタリなのですが、お口の中で合わせると、ほんの少しのすき間ですが、2次的にむし歯になる可能性がありますので、申し訳ないですが、再度型を採って仮のふたをして、次回セットしていきます ”
・・・と。
ただ、この場合でも患者さまは
ここは下手なんだ~
と感じられる方もいらっしゃると思います。
それは確かにエラーがあり、患者さまにご迷惑がかかっているのですが、患者さまのことを考えてのこの現状での最善の処置として行っています。
少しのすき間くらいならセットしてしまえば分からないからいいか、という考えが自分として最も嫌なことなので。。。
少しでも自分の考えが伝わっていただけるとありがたいです。
だ液の役割
またまた久しぶりの更新になってしまいましたが。。。
ところで、だ液って普通にあるものなので、あまり意識していないと思いますが結構大切なのです。
だ液は、噛めば噛むほどたくさん出てきて食べもの(異物)を消化吸収しやすくします。
ご飯やパンをよく噛んでいるとだんだん甘く感じてきますが、これはだ液の消化酵素のアミラーゼが、でんぷんをより消化吸収しやすい麦芽糖に変えてしまうからです。
1日に出るだ液の量は、大人の方で約1.5Lで、寝ているときは殆ど出ないのですが、噛むと通常の5~10倍量がでます。
また、その他にも口の中を流れてきれいにする自浄作用や、酸性に傾いた口の中を中和し、できかかったむし歯を再石灰化してエナメル質を修復するという大切な働きもあります。
さらには、細菌の増殖を抑制するリゾチウムが入っているので、抗菌作用もあります。
最近では、これだけではなく
・食品添加物の発ガン作用を抑え、活性酸素を減らしたり、
・細胞の新陳代謝を促して皮膚や胃腸の粘膜を丈夫にしたり、
・神経細胞の修復を促し認知症を防いで若々しさをたもったり
などのホルモンと同じような働きもしていることも分かってきています。
このように
“ よく噛んで食べなさい ”
というのはだ液がよく出るようにというのも1つの大きな理由だと思います。
もちろん、顎の発達、噛み合わせのこともありますが。。。
だ液については、ドライマウスや口臭との関連もありますので、しばらくしたら、それについても書いていこうと思います。
ところで、だ液って普通にあるものなので、あまり意識していないと思いますが結構大切なのです。
だ液は、噛めば噛むほどたくさん出てきて食べもの(異物)を消化吸収しやすくします。
ご飯やパンをよく噛んでいるとだんだん甘く感じてきますが、これはだ液の消化酵素のアミラーゼが、でんぷんをより消化吸収しやすい麦芽糖に変えてしまうからです。
1日に出るだ液の量は、大人の方で約1.5Lで、寝ているときは殆ど出ないのですが、噛むと通常の5~10倍量がでます。
また、その他にも口の中を流れてきれいにする自浄作用や、酸性に傾いた口の中を中和し、できかかったむし歯を再石灰化してエナメル質を修復するという大切な働きもあります。
さらには、細菌の増殖を抑制するリゾチウムが入っているので、抗菌作用もあります。
最近では、これだけではなく
・食品添加物の発ガン作用を抑え、活性酸素を減らしたり、
・細胞の新陳代謝を促して皮膚や胃腸の粘膜を丈夫にしたり、
・神経細胞の修復を促し認知症を防いで若々しさをたもったり
などのホルモンと同じような働きもしていることも分かってきています。
このように
“ よく噛んで食べなさい ”
というのはだ液がよく出るようにというのも1つの大きな理由だと思います。
もちろん、顎の発達、噛み合わせのこともありますが。。。
だ液については、ドライマウスや口臭との関連もありますので、しばらくしたら、それについても書いていこうと思います。
だ液の役割
またまた久しぶりの更新になってしまいましたが。。。
ところで、だ液って普通にあるものなので、あまり意識していないと思いますが結構大切なのです。
だ液は、噛めば噛むほどたくさん出てきて食べもの(異物)を消化吸収しやすくします。
ご飯やパンをよく噛んでいるとだんだん甘く感じてきますが、これはだ液の消化酵素のアミラーゼが、でんぷんをより消化吸収しやすい麦芽糖に変えてしまうからです。
1日に出るだ液の量は、大人の方で約1.5Lで、寝ているときは殆ど出ないのですが、噛むと通常の5~10倍量がでます。
また、その他にも口の中を流れてきれいにする自浄作用や、酸性に傾いた口の中を中和し、できかかったむし歯を再石灰化してエナメル質を修復するという大切な働きもあります。
さらには、細菌の増殖を抑制するリゾチウムが入っているので、抗菌作用もあります。
最近では、これだけではなく
・食品添加物の発ガン作用を抑え、活性酸素を減らしたり、
・細胞の新陳代謝を促して皮膚や胃腸の粘膜を丈夫にしたり、
・神経細胞の修復を促し認知症を防いで若々しさをたもったり
などのホルモンと同じような働きもしていることも分かってきています。
このように
“ よく噛んで食べなさい ”
というのはだ液がよく出るようにというのも1つの大きな理由だと思います。
もちろん、顎の発達、噛み合わせのこともありますが。。。
だ液については、ドライマウスや口臭との関連もありますので、しばらくしたら、それについても書いていこうと思います。
ところで、だ液って普通にあるものなので、あまり意識していないと思いますが結構大切なのです。
だ液は、噛めば噛むほどたくさん出てきて食べもの(異物)を消化吸収しやすくします。
ご飯やパンをよく噛んでいるとだんだん甘く感じてきますが、これはだ液の消化酵素のアミラーゼが、でんぷんをより消化吸収しやすい麦芽糖に変えてしまうからです。
1日に出るだ液の量は、大人の方で約1.5Lで、寝ているときは殆ど出ないのですが、噛むと通常の5~10倍量がでます。
また、その他にも口の中を流れてきれいにする自浄作用や、酸性に傾いた口の中を中和し、できかかったむし歯を再石灰化してエナメル質を修復するという大切な働きもあります。
さらには、細菌の増殖を抑制するリゾチウムが入っているので、抗菌作用もあります。
最近では、これだけではなく
・食品添加物の発ガン作用を抑え、活性酸素を減らしたり、
・細胞の新陳代謝を促して皮膚や胃腸の粘膜を丈夫にしたり、
・神経細胞の修復を促し認知症を防いで若々しさをたもったり
などのホルモンと同じような働きもしていることも分かってきています。
このように
“ よく噛んで食べなさい ”
というのはだ液がよく出るようにというのも1つの大きな理由だと思います。
もちろん、顎の発達、噛み合わせのこともありますが。。。
だ液については、ドライマウスや口臭との関連もありますので、しばらくしたら、それについても書いていこうと思います。
審美的な部分入れ歯
1本でも歯がなくなると、噛みにくい・しゃべりにくい・見た目が悪いなどのいろいろな不都合だけでなく、他の残っている歯が気が付かないうちに動いてたおれてきたり、伸びてきたりしてさらに機能的にも困ってしまいます。
なので、何らかの方法で修復(補う)しなめればならないのですが、方法としては
1. 部分床義歯(部分入れ歯)
2. ブリッジ
3. インプラント
などによるものがあります。各方法でそれぞれ長所・短所はあります。
(ホームページの“ 歯を失ってお困りの方へ ”参照)
ここで一番削ったり、外科をしたりの侵襲(しんしゅう)が少ないのは “ 部分入れ歯 ” です。
一般的にブリッジは、抜けた(抜いた)歯の両隣りに歯が残っていない場合にはできないので、奥に歯が残っていない場合には保険内の処置では入れ歯で補うことになります。
また、たとえ奥歯が残っていても、失った歯の本数が多いとブリッジを支える歯の本数が多くなる(健全な歯を削る確率も高くなる)ので、入れ歯を選択したり・ブリッジと入れ歯を組み合わせたりする場合もあります。
部分入れ歯の構造としては
・人工歯 (硬いプラスティック陶材などの歯)
・クラスプ(部分入れ歯を維持する金属のバネ様の引っ掛け)
・義歯床 (歯のない粘膜部分と接する歯ぐき色の部分)
などですが、最近は主に
『 前歯などのみえる範囲にクラスプが見えるのがイヤ! 』
という方のために “ ノンクラスプデンチャー ”
というクラスプを使用しないものがでてきています。
以前は白いクラスプ(アセタルという材料)で金属を使用しないものもありましたが、金属より強度が弱いためクラスプが太くなるので見た目もさほどよくならなかったり、舌感も悪かったりであまり使用されなくなってきたように感じます。
当医院でも最近、ノンクラスプデンチャーを2症例しました。
(そのうち画像ホームページでもアップしていく予定です。)
1症例は、右上奥歯2本の入れ歯ですが、金属アレルギーで金属を使用しない方法希望(インプラントの外科もできればしたくない)とのことで製作し、
もう1症例は、左上前歯2本の入れ歯ですが、その両脇がそれぞれ5~7本ブリッジの支台になっているので、ブリッジにするにはすべて除去しなければならないため外さないでの処置希望とのことで製作したものです。
遠くからの見た目でも、クラスプがないため殆ど目立ちません。ただ、クラスプを使用しないために適合がピッタリなので慣れるまでは取り外しに通常の入れ歯よりは、多少時間がかかると思いますが、長くても1ヶ月程度で違和感も感じにくくなると思います。
もし気になる方がいらっしゃるようでしたら、ご相談下さい。
ブリッジ・インプラントについても順次記載していく予定です。
なので、何らかの方法で修復(補う)しなめればならないのですが、方法としては
1. 部分床義歯(部分入れ歯)
2. ブリッジ
3. インプラント
などによるものがあります。各方法でそれぞれ長所・短所はあります。
(ホームページの“ 歯を失ってお困りの方へ ”参照)
ここで一番削ったり、外科をしたりの侵襲(しんしゅう)が少ないのは “ 部分入れ歯 ” です。
一般的にブリッジは、抜けた(抜いた)歯の両隣りに歯が残っていない場合にはできないので、奥に歯が残っていない場合には保険内の処置では入れ歯で補うことになります。
また、たとえ奥歯が残っていても、失った歯の本数が多いとブリッジを支える歯の本数が多くなる(健全な歯を削る確率も高くなる)ので、入れ歯を選択したり・ブリッジと入れ歯を組み合わせたりする場合もあります。
部分入れ歯の構造としては
・人工歯 (硬いプラスティック陶材などの歯)
・クラスプ(部分入れ歯を維持する金属のバネ様の引っ掛け)
・義歯床 (歯のない粘膜部分と接する歯ぐき色の部分)
などですが、最近は主に
『 前歯などのみえる範囲にクラスプが見えるのがイヤ! 』
という方のために “ ノンクラスプデンチャー ”
というクラスプを使用しないものがでてきています。
以前は白いクラスプ(アセタルという材料)で金属を使用しないものもありましたが、金属より強度が弱いためクラスプが太くなるので見た目もさほどよくならなかったり、舌感も悪かったりであまり使用されなくなってきたように感じます。
当医院でも最近、ノンクラスプデンチャーを2症例しました。
(そのうち画像ホームページでもアップしていく予定です。)
1症例は、右上奥歯2本の入れ歯ですが、金属アレルギーで金属を使用しない方法希望(インプラントの外科もできればしたくない)とのことで製作し、
もう1症例は、左上前歯2本の入れ歯ですが、その両脇がそれぞれ5~7本ブリッジの支台になっているので、ブリッジにするにはすべて除去しなければならないため外さないでの処置希望とのことで製作したものです。
遠くからの見た目でも、クラスプがないため殆ど目立ちません。ただ、クラスプを使用しないために適合がピッタリなので慣れるまでは取り外しに通常の入れ歯よりは、多少時間がかかると思いますが、長くても1ヶ月程度で違和感も感じにくくなると思います。
もし気になる方がいらっしゃるようでしたら、ご相談下さい。
ブリッジ・インプラントについても順次記載していく予定です。