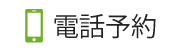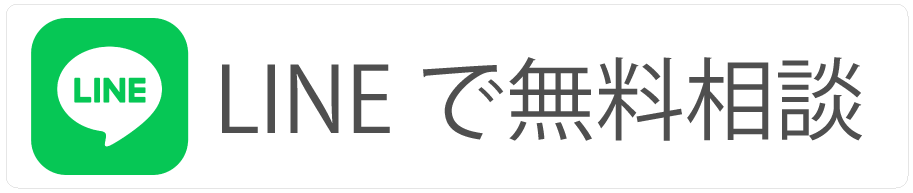これは歯ブラシの種類によくある毛の硬さを表しているものです。
この硬さはJIS(日本工業規格)という国家標準で定められていて、毛の長さを7mmにそろえて、ある面に毛を押しつけ、その負荷を計測して決めているのです。
JIS規格には
やわらかめ (ソフト)
ふつう (ミディアム)
かため (ハード)
の3種類しかありません。
しかし、実際には家庭品質表示法はJIS規格に従わなければいけないのですが、それ以外の場所への記載は各社がそれぞれ考えて、
『 実際の磨き心地 』
も伝えようとしているのです。
どういうことかというと、家庭品質表示は
「 やわらかめ 」 ですが、それ以外の目立つ場所には 「 ウルトラソフト 」 と記載してあったり、
「 かため 」 で家庭品質表示してある商品でも、目立つ場所には 「 ミディアム 」 と記載してあったり、 「 ミディアムソフト 」 「 ミディアムハード 」 などと大きく記載してあるものもあるのですが、JISにはそのような区分はないのです!
最近でた歯ブラシでトルネード毛という毛がネジってあるものもありますが、これは普通の太さよりも弾力があり
「 やわらかいのにコシがある・・・さらにしなやか ! 」
という表現ができるものもあるそうです。
歯ブラシの毛の硬さ1つでもいろいろあるものですね! ^^
がんと歯科って関係あるの?
じつはがんの治療中は、口にさまざまなトラブルが起きやすくなります。アメリカの国立がん研究所のホームページにも載っている有名なデータによると、たとえば抗がん剤治療を受ける人の40%に口内炎などが起こります。さらに強い抗がん剤を使う骨髄移植や白血病の治療では80%の口にトラブルが起きます。口の周りに放射線治療を行う場合は、じつに100%の割合で口内炎などのトラブルが起きます。
以前は、こうした副作用は、仕方のないこととされてきました。ところが治療が進歩し、手術も攻めの手術になり、昔なら切り取れなかったものも10数時間という長い時間をかけて切除するようになりました。また、抗がん剤が強くなるにつれて、口内炎などの副作用も以前よりつらいものになってきました。
医科と歯科が連携してサポート!
こうした状況下で、静岡県立がんセンターの大田洋二郎先生らが取り組んでいた歯科の支持療法の成果が注目を集め、多くのがん治療の専門病院が「歯科の支持療法を取り入れたい」と模索するようになりました。
そこで日本歯科医師会では、国立がん研究センターの大多数の患者さんの居住圏である東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、山梨県の歯科医師会に協力してもらい、関東圏に連携モデルを構築することにしました。質の高い支持療法を実現できるよう、連携のための講習カリキュラムを作り、会員を呼びかけて、手を挙げた歯科医師に講習会を受けてもらうのです。
こうして数年間で関東5都県だけで2、600人の歯科医師が講習1・2の受講を終え(2013年6月時点)、現在ではがんセンターの患者さんが、お住いの近くの登録歯科医院を名簿から選び、安心して受診できる体制が整っています。
また、関東圏で構築されたモデル連携事業のノウハウは、全国の都道府県歯科医師会に伝達され、国が後押しをする形で各地域のがん医療連携拠点病院などとの連携をはじめています。
がんとの闘いを有利に進めよう!
現在は、副作用の苦しみをゼロにはできないまでも、「やれることはなんでもやろう」「しんどい期間を少しでも短くしよう」という観点から、合併症の原因となる口のなかの細菌を減らすため、がん治療をはじめる前に歯科で口腔ケアを受けることが必須となっているのです。「がん治療を受けることになったらまず〈歯科〉へ」。このことを忘れないでください。
引用参考文献:nico 2013年5月号

顔立ちを決めるのは、頭蓋骨
骸骨から生前の顔を再現する「復顔術」ってご存じですか?犯罪捜査や考古学で用いられ、かなり正確に生前の顔立ちを復元できる手法です。顔の皮膚や筋肉の厚みは個人差が少ないため、頭蓋骨を一定の厚みの粘土で覆っていくと、人の顔立ちがクッキリと浮かび上がります。じつは私たちの顔立ちを決定づけているのは、皮膚でも筋肉でもなく、骨格です。美人が美しいのは、頭蓋骨が美しいということなのです。
きれいになるのは歯並びだけじゃない?
頭蓋骨は、一番上の丸い脳頭蓋、真ん中の上あご、そして下あご、と3層構造になっています。美しい人の骨格はこの3層の大きさのバランスが非常によく、その結果フェイスラインがスッキリとして見えるのです。
なんのためにこんな話を始めたのかというと、「矯正治療とは、ただ歯を並べるだけの治療ではない」ということをご理解いただきたいからです。矯正治療とは、脳頭蓋を基準にして、上あご、下あごの歯や歯槽骨を含めた骨格にアプローチし、よりバランスの取れた噛み合わせへと導く治療です。
たとえば、子どもの矯正治療は、成長発育のスパートがはじまる以前から、より良い骨格へと育つよう導く治療です。たとえば下あごが小さく上あごの目立つ出っ歯さんなら、下あごがもっと育つように導いて調和させます。
噛む筋肉や顎関節の機能がまだ完成されていないうちに骨格のバランスを改善しておくと、15〜16歳で完成を迎えるころには、骨格と調和したきれいな歯並びと噛み合わせが手に入れやすくなります。これが子どもの矯正治療です。
矯正治療で、口もと・骨格美人に!
一方、おとなの場合は、あご本体は完成しているので、成長発育の勢いを使ってあごの大きさごと導けるようなアドバンテージはありません。しかし、歯を動かすことで歯槽骨のかたちを変え、上あごと下あごのバランスをより調和させて見せることはできます。
完成されたおとなの骨格でも、こうして硬組織にアプローチすることで、よりバランスの取れた美人の頭蓋骨に近づけることができるのです。
おとなの矯正治療では、機能面の改善はもちろん、美しさの獲得も大切なテーマです。あなたも矯正治療で骨格ごと美人になってみませんか?
引用参考文献:nico 2013年5月号
突然ですが、こんな症状ありませんか???
①. 口をあけようとすると耳の近くが痛い!
②. 顎を動かす時に音がなる!
③. あまり大きく口があかない
④. その他頭痛などのさまざまな症状
もし心当たりがあるなら 『 顎関節症 』 の可能性があります。
この 『 顎関節症 』 とは、通常お口の開閉、咀嚼(そしゃく)、発音時に
顎関節(上あごと下あごのつなぎを構成している軟組織・あごの骨・筋肉をふくむ総称)
に痛みや音が鳴るなどの不快症状を伴う状態で、何らかの原因が生じて異常をきたすのですが、その原因としてはいくつかありそれらが積み重なってある限界を超えたときに発症する・・・と考えられています。
ただし、なりやすい人やなりにくい人がいて
くいしばりや歯ぎしり、偏咀嚼(いわゆる片咬み)
などの生活習慣の中の要因の積み重ねが
その人の限界を超えた時
に発症するのです。
他の原因となる生活習慣としては
・ ストレス
(筋肉を緊張させてくいしばりを起こしたり、夜間の歯ぎしりを促したりする)
・ 悪い噛みあわせ
(咀嚼筋やブラキシズムの原因として関連している)
・ 顎や筋肉に負担をかける癖や習慣
(うつぶせ寝、頬杖をつく癖、顎の下に電話を挟む、猫背の姿勢など・・・)
などが挙げられます。
では、どこに気を付ければよいのか?という点は具体的に書くと
・ 固い物やガムを噛む事が多い人は、しばらく意識して止めてみる。
・ 歯をくいしばるクセのある人も気をつけて止めるように努力する。
・ 片方の歯だけで咬む癖はすぐに止める。
・ 寝姿(うつぶせ寝や横向きを直す。
・ 猫背のクセを直す。
・ 偏った姿勢を直す。
これらに気を付けたとしても、いったん顎関節症の症状が出てしまうと専門的な診断と治療が必要になるため、かかりつけの歯科医院を受診しましょう! ^^
(※ 今回の内容は 「 都城歯科医師会 」 のリーフレットを参考に記載しています。)
①.生まれたばかりの歯はとても弱い!
赤ちゃんの肌がやわらかくてかぶれやすいのと同じように、生まれたばかりの歯はとてもやわらかく、むし歯菌(ミュータンス菌など)がつくる酸にとてもよわい状態です。
そのため、生えたての歯は穴があきやすく進行がとても早いです。歯はだ液中のカルシウムなどを吸収して時間をかけて強い歯になっていきます。
またフッ化物はカルシウムなどの吸収を助けてくれるので、積極的に利用されることをおすすめいたします。
まずは丈夫な乳歯に育てることが丈夫な永久歯への第一歩です。
②.むし歯菌はどこからくるの?
むし歯菌は生まれたばかりの赤ちゃんの口には存在しません。赤ちゃんのむし歯菌は母親などからの口うつしの食事、同じ箸やスプーンからうつるとされていますが、父親や兄弟、お友達からうつる場合もあります。
家族はもちろん、特に赤ちゃんと接する機会の多い母親はお口のケアが特に大切になります。
歯科人間ドック
あまり聞きなれない言葉ですが、受診者は年々増加しているそうです。
これからは、定期的な歯科検診を積極的に受診するような時代になり、そこで歯科人間ドックを通して口腔保健に関する意識の向上をはかるというもの。
人間ドックはなんと昭和29年に始まったそうですが、歯科人間ドックに関しては
平成10年に 『 日本歯科人間ドック学会 』
が設立され、平成18年から認定医制度を導入してきました。
この学会では、
口腔内疾患の早期発見による早期治療のみではなく、口腔の健康度やさらには全身疾患についてもスクリーニングが可能な検査項目を考案しています。
自分も6年前の開業当初から、アンチエイジングとともに歯科人間ドックに関心がありました。
ただ導入には躊躇していたのです。
歯科疾患は慢性的な経過をたどるため、初期では自覚症状がなく、さらにほとんどの人が経験しているため軽視されがちな現状があります。
定期的な歯科ドックを受けると。。。
1. 口腔の健康維持
2. 早期治療による医療費の軽減
3. 診療時間の縮小や回数の短縮
4. 身体への影響(歯を削る、抜く)が減少
5. 全身疾患の悪化を防ぐ
6. アンチエイジング
など多くのメリットがあります。
なので、これからのために1日も早く当医院でも歯科ドックが受診できるように体制を整えていきたいと思います。
よく耳にする
『 プラーク 』
という言葉。これは細菌がかたまってできたもの。
わずか 1mgに1億個の細菌が存在しています!
口の中には、人間の体の中で最も多くの種類の細菌が存在しています。
特に気をつけたいのが、むし歯や歯周病、口臭など口に関する多くのトラブルの原因になっている
“ 歯垢 ( しこう 、プラーク )
です。
このプラークはただの食べかすだと思っている人も多いようですが、これは歯の表面に付着して増殖する生きた細菌のかたまりなのです。
歯に強く付着しているプラークは、粘着性があり、うがいでは除去することができません。
そのため、毎日の歯みがきでプラークをしっかり取り除くことが大切です。
このプラークの中には、むし歯の原因菌であるミュータンス菌や歯周病菌などが存在していて、磨き残しがあるとプラークが歯の表面に付着したままになるので口の中が危険な状態にさらされてしまいます。
食後の歯みがきでプラークをきちんと除去し歯と口の健康をこころがけましょう。
妊娠中はエストロゲンという女性ホルモンが増えるので、歯ぐきのトラブルも起こりやすくなります。
女性ホルモンの影響で、歯周ポケットにいる普段は害のない細菌が増えて炎症を引き起こしてしまうためです。
また、つわりなどで歯磨きもおっくうになりますが、もちろんブラッシングが不十分だと歯周病の細菌も増えてしまいます。
歯磨きにまさる予防法はないので、大変だとは思いますがブラッシングはかかさずに行いましょう! ^^
生まれてくる赤ちゃんのためにも必要最小限の3つは守りましょう!!!
①. 歯と歯ぐきの境目を丁寧にみがく
歯ぐきの炎症は、お口の中を清潔にしておけばある程度は防げるので特に歯と歯ぐきの境目は要チェックです。
②. 定期的に歯医者さんでチェックしてもらう
身重な妊娠中は、歯みがきすら面倒な時もあるので、磨けているつもりでも実際には磨けていないこともあります。
その点歯医者さんで定期的にチェックを受けていれば安心です。
③.タバコは吸わない!!!
妊娠中のタバコが胎児によくないことは常識ですが、タバコは歯ぐきにもよくないことが分かっているのでお口にも体にも百害あって一利なし、です。
健康な歯ぐきを保って元気な赤ちゃんを産みましょう !
( ※ 今回は オーラルケア さんのリーフレットを参考に記載しています。 )
今日は診療後に歯科医師会館で6月8日の
「 お口の健康フェスティバル 」
での講演会のプレ講演会がありました。
タイトルはその内科医の先生の著書の1つですが、なかなか興味深いタイトル!
で、今回の講演会のタイトルも
『 口呼吸が万病の原因(あいうべ体操で鼻呼吸へ!) 』
~ 人間本来の鼻呼吸で免疫アップ! ~
です。
このお話しを聞いて早速著書のうち2冊購入しました。


“

いのちにかかわる眠りの病気
「睡眠時無呼吸症候群」という病気をご存じですか?運転士が居眠りをして新幹線の停止位置を間違えた事故でこの病気が大きく取り上げられて以来、日本でも広く知られるようになりました。
この睡眠時無呼吸症候群は、「いびきをかいて寝ている」と思って聞いていると、突然のどが詰まったような「クッ」あるいは「カッ」という音がして、そのあと「……」と10秒以上呼吸が止まります。その後、息苦しそうな大きないびきが再開するという、気道の閉塞が原因の深刻な病気です。
呼吸が苦しく、眠りが浅くなるため、からだは休息を必要としているにもかかわらず、いくら寝ても休息になりません。放っておくと、いのちを縮めてしまうこともある、怖い病気なのです。
いびきはからだの悲鳴!
もうひとつ、気をつけていただきたいのが「いびき」による不眠症です。いびきは、寝息に近いようなあまり問題のないものもあり、ほとんどは単なる騒音として片付けられがちです。ところがいびきの原因の正体も、程度の差こそあれ、睡眠時無呼吸症候群と同じ気道の閉塞なのです。
「いびきをかいて寝ている」というと、グッスリと眠っているイメージがあり放置しがちですが、現実はその逆。いびきは、眠りの邪魔をするやっかいものです。
なぜ歯科でいびきの治療を?
こうした不眠症は、眠れないからといって、いくら眠り薬などを処方してもらっても改善はしません。原因の根本は気道の閉塞、つまり気道が物理的に塞がれてしまうことが問題だからです。
横になったとき、ダラリと気道のほうへ下がってしまう舌や軟口蓋がトラブルのおおもとなら、それをなんとかしないかぎり、改善は望めません。口のなかの治療、といえば、歯科治療の領域内ですよね。というわけで、いびきが引き起こす不眠症の治療は、歯科で受けることができます。ただし、現在の健康保険制度の規定では、治療を保険診療で受けるための「診断」は、医科で受けなければなりません。
そのため、まずは耳鼻咽喉科や呼吸器内科、睡眠センターなどに受診して保険適応を診断してもらったうえで、具体的な治療は歯科・口腔外科や専門知識のある歯科医師が行うことになります。「もしかしたら」と思うかたは、お早めに専門の医療機関に受診なさることをおすすめします。
引用参考文献:nico 2013年7月号




 “
“