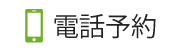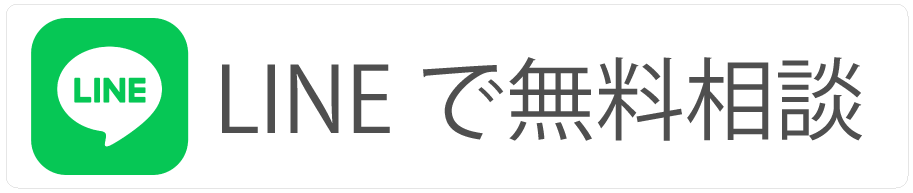むし歯の原因の1つでもありますが、歯ぐきの腫れの原因の1つに 「 プラーク 」 の毒素があります。
プラークとは、歯の表面に見られる付着物のことで、以前から 「 歯垢;しこう 」 「 歯苔;したい 」 とも呼ばれていました。
しかし、その後の研究により
プラークとは、歯の汚れや垢というよりも細菌がパックされたもの
ということが分かってきました。
つまり、プラークはむし歯や歯周病の原因となる最近の塊なのです。
これは、最近の塊ですがプラーク1mgあたりには何と10億個もの細菌が存在するといわれています。
ということは、ツマヨウジの先に目に見える程度のプラークをとると、そこにはおそらく数百億個の細菌がくっついていることになります。
プラークの話をする時によくでてくる言葉に
「 バイオフィルム 」
があります。
これはヌルヌルした気質(菌体外多糖と粘液層)と水のあるところに形成されます。
身近な例としては、台所の排水口に見られる 「 ヌメリ 」があげられます。
この 「 バイオフィルム 」 は口の中でも形成されます。
プラークとも似ていますが、ちょっと違うのは
“ バイオフィルムは最近どうしが情報を伝達し合いながら生きている ”
という点です。
プラークとバイオフィルムには、ちょっとした定義の違いはありますが
「 デンタルプラークは口腔内に形成されるバイオフィルム 」
ともいわれています。
なので、広い意味では、プラークもバイオフィルムも同じもの、といえます ^^
※ この記事は 「 月刊 歯科衛生士 」 2015年 1月号 を参考に記載しています ^^

歯周病の検査を受けましょう!
「歯周病は、いつの間にか歯が抜ける怖い病気だ」ってよく言われますよね。でも歯周病は本来、そんな怖い病気ではありません。多くの場合、症状の進行は緩やかですし早めに病気に気づくことができれば予防も治療も、ちっとも難しくないのです。それなのに歯周病で苦しむ患者さんがあとをたたないのはなぜでしょう?問題は、手遅れ症例が多いということです。
歯周病は、「沈黙の病」と呼ばれるほど見逃しやすい病気です。痛みなどの自覚症状がなく、歯みがきで出血したりしても、つい受診を先延ばしにしているうちに、手の施しようがなくなってしまうのです。そのため、ご自分の歯ぐきの中がどういう状態なのか、治療が必要なのかどうかを知るには、歯周病検査できちんと調べる必要があるのです。
歯肉炎か歯周炎か、それが問題だ!
じつは私たち歯科医師は、「歯周病」と総称されている病気のことを、症状の進行の程度によって、「歯肉炎」と「歯周炎」に分けてとらえているんです。
まず「歯肉炎」ですが、これは歯周病の初期症状。歯ぐきの腫れだけですんでいます。歯槽骨は破壊されず、歯と歯ぐきをピタッと付着させている組織も失われていません。そのため。歯みがきと歯石取りで炎症を止めれば、すっかり元の健康な状態に戻ります。
一方「歯周炎」は、歯を支える歯周組織がすでに破壊され始めている状態を言います。歯みがきと歯石取りで炎症を治し、病気の進行を止めますが、残念ながら失われた付着と歯槽骨は元どおりにはなりません。ただし早期に気づいて炎症を止め、再発を防いで維持すれば、歯をしっかり守っていくことができます。
再発予防にはメインテナンスが必須!
歯周炎の治療をした患者さんの歯ぐきは、キュッと引きしまり治ったように見えます。ところが、健康な人よりも歯周ポケットが深い分、プラークが溜まりやすく歯石も付きやすいのです。「治療が終わった!」と油断していると、歯周ポケットの中にまた歯石がガチガチに付き、治療が一からやり直しになってしまいます。
何度も通ってしっかりと治療を終えホッとしたら、今度は治療のためではなく、検診と、歯周ポケットの中まできれいにできるプロのクリーニングを受けるために、定期的に歯科医院においでください。
治療の終わりは、再発予防のはじまりです。歯科医院との新たなお付き合いをぜひスタートさせましょう。
参考引用文献:nico 2015年4月号
レーザー治療とは、強いエネルギーを持った特殊な光を患部に照射して行う治療です。
組織の吸収された光が熱エネルギーに変化し、分子構造を破壊して患部に作用して治療効果をもたらします。
咀嚼トレーニングで期待できる歯列成長促進と咬合適応力の向上!
たった1本の歯が痛いだけで、
「 食事ができない 」 「 食欲がわかない 」
といった経験をしたことがある人は少なくないと思います。
特に中高年になると、歯周病で歯が動くようになったり、歯を失うリスクが高くなったりします。
このような年代では、健康に気を付けながら食べたいものを食べるというよりも、歯の状態に合わせて食べやすい食品を選択してしまいがちで、それが習慣化してしまいます。
たとえば、歯を失うと野菜の摂取が減り、逆に炭水化物の摂取が増えることが示されています。
よく噛めない人と何でも噛める人では、ミネラルやたんぱく質などの摂取にも差異がみられます。
また、歯や口の健康が食生活にもたらす影響は、栄養素ばかりではなく、よく噛むという食べ方が摂取エネルギーにも影響するのです。
よく噛むということが満腹感の形成を促すことは古くから知られています。
食べ過ぎの原因の1つは
『 早食い 』
です。満腹を感じる前にたくさんのエネルギーを摂ってしまうのは、満腹情報として食行動調節に主要な役割を果たしている消化管の機械的刺激や吸収後の代謝産物などの情報が 「 早食い 」 で機能しなくなるからです。
この習慣化した 「 早食い 」 を是正するためには、食べ過ぎていることを本人が自覚することと、一口20~30回噛むことが大切であり毎食後にできたかどうかを体重測定とともに記録する方法が効果的とされています。
そして、
「 一口量を少なく 」
「 次々口の中に食べ物を入れない 」
「 一口ごとに箸をおく 」
といった具体的な目標を本人が決めておき、それができたかどうかを記録することが有効です。
( まさに早食いで太ってしまった自分には耳の痛い話しですが。。。 今ダイエット中なので早速実践してみたいです ^^ )
歯科治療を受けることによって口腔内の状態は改善します。
歯周病と同じく生活習慣病である糖尿病治療では、食事指導を受ける前に歯の健康状態をチェックし、何らかの症状ある場合には歯科治療を受けることが必要ですが、それだけで満足するのではなく、健康的な食べ方を身に付けることが重要です。
歯の状態や食べ方が肥満の原因となり、この肥満こそが健康を損なう
のです。
患者さまが歯科治療で疑問に思うことの1つに、まずこれがあると思います。
『 根の治療が長くかかるな~??? 』
治療する歯が、今まで根の治療をしたことがなく根管内が感染していない場合は、炎症が落ち着くまでの回数も通常4~5回程度が多いです。
ただ、化膿して歯ぐきが腫れたりして感染してからの処置の場合は、毎回根管内をきれいにし、膿が早くなくなるような薬を入れますが、正直何回で終了とははっきり言えません!
以前薬をつめてある根管では、その堅く固まった薬をまず取り除かなければならないために、どうしても時間がかかるのです。
そのあとで、薬をしっかりすき間なくつめるために根管を拡大するのですが、複雑に曲がっていたりすると機械ですべて拡大することができず、手用器具で少しずつ拡大するために時間がかかるのです。
また前歯は根管数はだいたい1つですが、奥歯になると2つ~4つの根管数あるため、その根管数だけ2~4倍時間もかかるのです。
さらに、その方の状態でも回数変わりますが、同じ方でも極端に言えば、1本1本の歯の状態によっても回数は大きく変わりますので。。。
これが歯科医院への大きな不満の1つになっていることは分かっているのですが、これだけは何ともできないというかご理解いただきたいのです。
また治療が長期間になって痛みもないため、中断される場合もあると思いますが、次に痛みが出ると、また最初から治療費や治療期間が必要になるため無駄になります。
また最悪の場合は、抜歯になる可能性もあるので、せめて根の治療中だけは中断しないようにお願いいたします。 ^^
歯が1本だけ抜けたり、抜いたりした場合、多くの方は
“ 別にこのままでも食べられるし・・・ ”
って考えてしまいます。
もちろん、実際はそうなのですがその気持ちで長い年月過ごしてしまうと、後々後悔することになります。
1本だけと放っておくのではなく、すぐに抜けた部分を補う何らかの処置をしないと、歯全体のかみ合わせがダメになってしまいます。
歯が1本抜けると、隣の歯は抜けた歯の方向へだんだんと倒れてきます。
また同時に抜けた歯の上や下の今まで噛み合っていた歯は、ぶつかる相手の歯がないのでだんだんと延びてくるのです。
そうして延びた歯は、抜けた(抜いた)歯の隣の歯にあたり、ますます隣の歯を傾かせることになります。
こうして全体の噛み合わせのバランスが崩れ、他の歯も徐々に悪影響を受けていきます。
早めに治療を受けないと、だいぶ後になってから義歯(入れ歯)を入れようにも、前後の歯が傾いていて1本分の横幅のスペースがなかったり、噛み合わせの歯が延びてきて高さのスペースがなかったりします。
そうなると、この傾きを治したり、歯の高さをそろえてからでないとすぐに義歯を入れることもできず、治療に時間がかかることにもなります。
それなので、1本でも抜けたり(抜いたり)したら、歯科医の治療を受けたり、そのまま中断するのではなく継続して治療を受けることが大事になります。
そうしないと歯全体がダメになってしまうのです。。。
これだけは絶対にご注意下さいね ^^
私たちの口腔内には300種類を超える細菌が存在します。
これらの細菌は、歯や歯肉などの表面に付着し、菌同士が集まって集落のようなものを作ります。
この集まりがプラーク(歯垢)で、口の中には手入れが行き届いている人でも500億、ふつうの人で2000億、手入れの悪い人では一兆もの菌が存在するといわれています。
細菌は、エサになる栄養分がないと増えることはできないのですが、口の中にはいつも食べ物が入ってくるのでプラーク中の細菌が死滅することはなく、むし歯や歯周病の原因になっているのです。
ところで、むし歯も歯周病もプラーク中の細菌の感染が原因で起こりますが、それぞれの細菌はタイプがまったく異なります。
むし歯の原因菌となるのは、主に縁上プラーク(歯肉より上側で歯の表面に付いているプラーク)の中の細菌です。
好気性菌といって空気の存在下でよく繁殖し、空気に触れる菌の表面部分で活動します。
一方、歯周病の原因菌となるのは、歯肉縁下プラーク(歯肉の下にできた歯周ポケットに入り込んだプラーク)の中の細菌です。
こちらは嫌気性菌といって空気のないところでよく繁殖する菌で、空気に触れない歯周ポケットの中で増殖し、歯周病を悪化させます。
この歯肉縁下プラークは歯肉の中にあるので、普通に歯を磨いただけでは、歯肉縁上プラークほどきれいに落とすことができません。
歯肉縁下プラークは歯肉縁上プラークに比べ、毒性の強い物質を作り出す悪玉菌が多く、全身に悪影響を及ぼしやすいことも分かっています。
口腔内はもちろん、全身の健康を守るためには、この悪玉菌を増やさないことが大切なので、そのためにはプラークが増えないようにすることが重要です。
しかし、人が生きて口から何かを食べている限り、口腔内にはプラークが付着してしまいます。
そのまま放置すると、細菌がますます増えてしまうので、できるだけ早く歯を磨いてプラークを落とすほか手立てはありません。
こうしてプラークが増えすぎないように口の中の環境を整えていくことを
『 プラークコントロール 』
といいます。
結局は、これが歯周病をはじめとするすべての歯科疾患対策の基本になります。 ^^
歯石がたまれば歯によくないってきくけど。。。
・ 歯石はどうしてできるのか?
・ なぜ歯によくないのか?
歯石は歯の裏や根元などに文字通り石のように固くなってくっつき、簡単にいうと歯垢(しこう、プラーク)のなれの果てのようなものです。
もう少し詳しく言うと、歯垢の中のいろいろな細菌が歯磨きなどによって取り除かれなかった時にだ液の中の成分と結合して石灰化するものです。
この歯垢の中の細菌は、ほぼ2週間くらいで石灰化してしとたび石灰化がはじまると、その周りにまた細菌が群がってさらに石灰化し、歯石はますますガッチリと歯の外周を固めていきます。
歯石は、歯の根元近くにやや黄色みを帯びて固まりますが、そのとき歯の根元の歯肉に囲まれた部分、つまり外からは見えない部分に、より強固な歯石がついていることが多いのです。
そしてこれは確実に歯周病を悪化させます。
ですから、歯周病の治療にも予防にも、歯石はよく取り除いておかなければならないのです。
歯科医院では、むし歯治療のあとや定期健診の時など、機会あるごとに “ 歯石除去 ” をしています。
歯石除去は、スケーラーなどとよばれる金属の道具で一本一本手で取り除いていく作業が中心になります。
細い金属の棒の先端の刃の部分で歯にこびりついた歯石を取り除きますが、歯ぐきの根元から明らかに見えている部分では、超音波で歯石を除去するスケーラーも使用します。
歯の根元や裏側、そして歯肉の内側にまで、歯石はくっついていますから、歯石除去は大変な作業です。
歯肉の中にまでたくさんたまっていると、出血もあるので多少の痛みを伴う場合もあります。
また歯肉の中まで入り込んだ歯石を取り除く場合は、表面だけの麻酔や通常の注射の麻酔をする場合もあります。
そうして歯石除去した歯の表面はツルツルすべすべになり、しばらくは歯石もつきにくくなるため、軽い歯周病の方ならこれだけで終了する場合もあります。
それでも、また時間の経過とともに歯石はつくので、定期的な歯科医院の受診をしてこまめに歯石除去をおこないましょう ^^
むし歯の痛みにならんで多いのが
「 歯ぐきの痛み 」
これは歯周病の代表的な症状ですが、他にも原因はいろいろ考えられます。
たとえば、
①. 歯と歯ぐきの境目に小さなむし歯ができた場合・・・むし歯は直接は痛まない場合が多いですが、むし歯付近にたまった汚れによって歯ぐきに炎症が起こります。
②. むし歯で神経が死んでしまった場合・・・死んで腐った神経に触れている根尖部付近の骨に炎症を起こします。
③. 歯と被せ物のセメント(被せ物の接着剤)が破壊された場合・・・そのすき間にだ液や血液が入り込み、その破壊されたセメントが触れている歯ぐきに炎症を起こします。
④. レントゲンに写らないような亀裂が歯根に入った場合・・・その亀裂や破折したすき間に汚れがたまり、亀裂付近の骨や歯ぐきに炎症を起こします。
⑤. 神経をとった後、根尖部の閉鎖が不十分な場合・・・同様に根尖のすき間に汚れがたまり根尖部付近の歯ぐきに炎症を起こします。
これらの歯ぐきに起こる炎症には、口の中に生息している常在菌が深くかかわっています。
傷口に常在菌が入っただけでは炎症は起こりませんが、そこに異物と判断されるようなものが混在していると、炎症が成立して痛みとして症状が出てきます。
したがって、歯ぐきの痛みを察知した場合は、どこに痛みの中心があって異物と判断されるような原因がなんであるかを探らなくてはなりません。
このような痛みの発信場所と発信原因をできるだけ早く的確に見つけ出してその都度細かく対処していくことが望まれます。
歯根破折の場合、破折直後はまだ歯ぐきの炎症はありませんが、数日後に破折したすき間に汚れがたまってくると炎症が起こります。
しかし、その状態をさらに放置しておくと、破折片(割れたカケラ)は少しずつ移動してきて、最初は小さかったすき間も大きな空間となってしまいます。
なので銀歯が外れたりしたときは、実はいいチャンスなのだと思います。
その時に少しでもむし歯があったら歯科で指摘あると思いますが、
「 時間ないのでとりあえずつけて下さい 」
といわれると物理的にできないことはないので、処置しますが本意ではないです。
この時に現状でむし歯の処置をしてベストの対処をしておけば寿命はだいぶ延長できたと思いますが、場合によってはすき間がある状態で戻してつけるとむりな力がかかり破折の可能性が高くなります。
そうなると残された道は抜歯しかなくなります。
詰め物、被せ物がとれた時には何かのサインと考えてすぐに歯科医院でベストの対処方法をお願いしましょう!^^