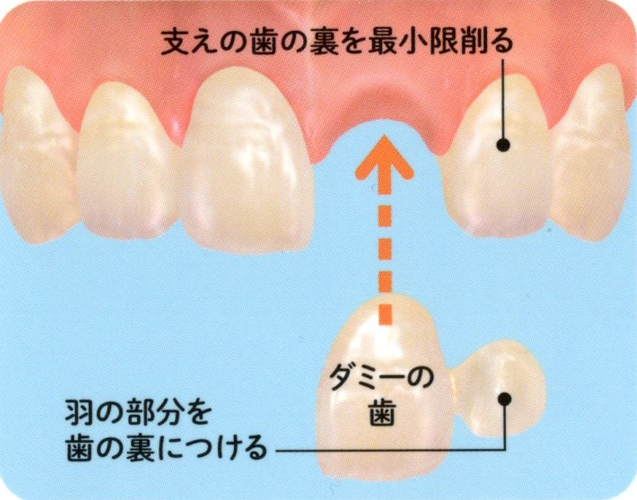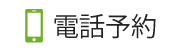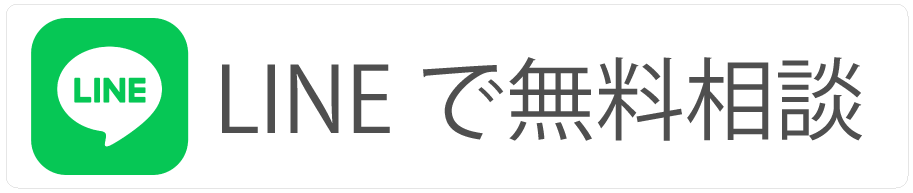歯のホワイトニングといえば、歯科の領域。でも世の中には、セルフホワイトニングサロンや美白効果のある歯みがき剤をはじめ、「歯を白くする」サービスや製品がたくさんあります。それでも歯医者さんのホワイトニングが選ばれるのはなぜなのでしょうか。
歯科医師の介在と薬剤の種類が違う
歯医者さんで行うホワイトニングとそうでないホワイトニング。まず違うのは、「歯科医師の診断や歯科衛生士の指導・サポートを受けられる」点です。最初に歯科医師がお口を診て、ホワイトニングが問題なくできるお口かを診断し、ホワイトニングを開始したら、しっかり効果が出ているか、適切に安全に使えているかを見守ります。
また、「使用する薬剤」も違います。歯医者さんのホワイトニングでは、過酸化水素(または過酸化尿素)を配合した薬剤を使用します。この薬剤には、「歯を本来の色より白くする」漂白効果があるのですが、歯科以外では使用が認められていません。
一方、歯医者さん以外のホワイトニングでは、歯科医師の介在はなく、歯の本来の色を取り戻す着色除去がメインとなります。
歯質強化のチャンスです!
ホワイトニングは、薬剤に配合されている過酸化水素や過酸化尿素が、歯の表面を覆う透明な保護膜「ペリクル」を除去し、漂白成分を浸透させることで起こります。
この「ペリクルがはがれる」というのが、じつは歯を強化するまたとないチャンス。ペリクルがはがれた状態は、唾液中のカルシウムやリン酸、歯みがき剤などのフッ素(フッ化物)が歯に吸収されやすい状態です。だから、ホワイトニング直後にフッ素やCPP-ACP(非結晶性リン酸カルシウム)を塗布すると、歯を強くする効果が非常に高いのです。
殺菌作用も期待できます!
ホワイトニングの薬剤は、消毒薬にも使われるオキシドールの仲間。殺菌作用があるのでお口の中全体のむし歯菌や歯周病菌を減らす効果が期待できます。
特にホームホワイトニングでは毎日決められた時間、歯に薬剤を作用させるので、さらに効果は増加すると考えられます。
歯医者さんのホワイトニングは、自費治療のため確かにお金がかかります。ですがこれらの違いを考慮すると、決して費用対効果、つまりコストパフォーマンスは悪くないといえるのではないでしょうか。
引用参考文献:nico2023年4月