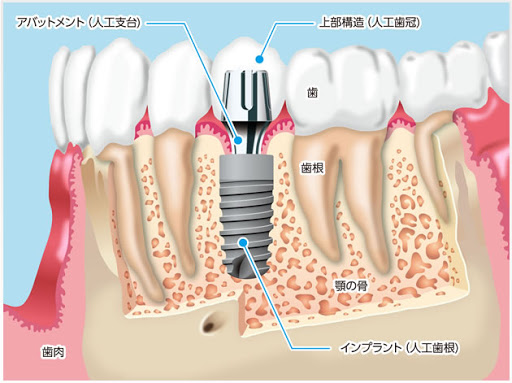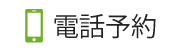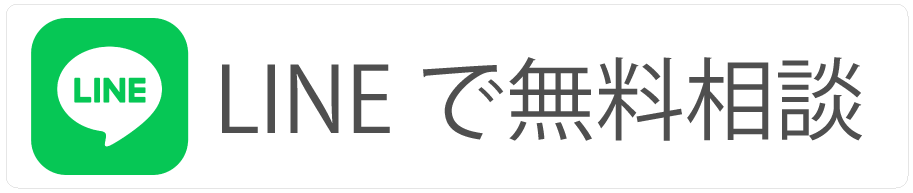歯並びに舌とくちびるが影響?!
歯はきれいな馬蹄型に生えるのが当たり前だと思われがちですが、この馬蹄型は、歯と接しているくちびるや舌の筋肉から加わる力の支え合いによって生まれています。なぜなら、歯は力を与えられると、その方向にジワジワと動いていくからです。
言いかえれば、歯は舌の力とくちびるの力のバランスが釣り合うところへと動き、並んでいます。とくに歯の生え替わり時期のお子さんの場合、
・乳歯が抜けた部分など、気になるところをつねに舌で触っている。
・飲み込むときに舌で歯を押している。
・お口をいつもポカンと開けている。
というように、お口の癖が、歯にかかる舌やくちびるの力のバランスを崩していると、その影響で歯は前へと動き、噛み合わせも崩れていってしまいます。
舌には理想的なポジションがある
歯に加わる力のバランス、ひいては歯並びを乱す原因となりやすいのが「舌」です。 いまこれを読んでいるあなた、舌の先はお口の中のどこに触れていますか。上あごの天井付近ですか。それとも前歯ですか。
じつは舌には、収まるべき正しい位置があります。リラックス時に舌が上あごの天井につきつつ、舌先は前歯に触れないか、触れたとしてもほんの軽く触れるくらいの位置が理想です。
対して、舌が上あごにつかず、低い位置にあり歯にもたれかかっていると、常に歯に力が加わってしまいます。
また、舌の癖は矯正治療の妨げにもなります。舌からかかる力のせいで、矯正装置を入れても想定したほど歯が動かなかったり、治療が済んで装置を外した後に後戻りを起こしてしまうことがあるのです。
トレーニングで正治療がスムーズに
こうした癖を改善し、矯正治療をスムーズに進めるために役立つのが「お口のトレーニング」です。舌を上あごの天井に当てる、舌を上に持ち上げる力を鍛える、奥歯を噛みしめて噛む力を強くするなどの練習を、矯正装置の装着と並行して(または単独で)繰り返していただきます。これは専門的には「MFT:口腔筋機能療法」といい、舌をはじめとしたお口まわりの筋肉のバランスを整える効果があります。
ただし、トレーニングはすぐに効果が出るものではありません。長期間、毎日繰り返していただくことで、徐々に効果が表れてくるものです。慣れるまでは舌が疲れたり痛くなりますし、時間も根気も必要となります。ですが、素敵な歯並びのために大切なことですので、歯医者さんといっしょに根気よくがんばっていきましょう!
引用参考文献:nico2020年2月



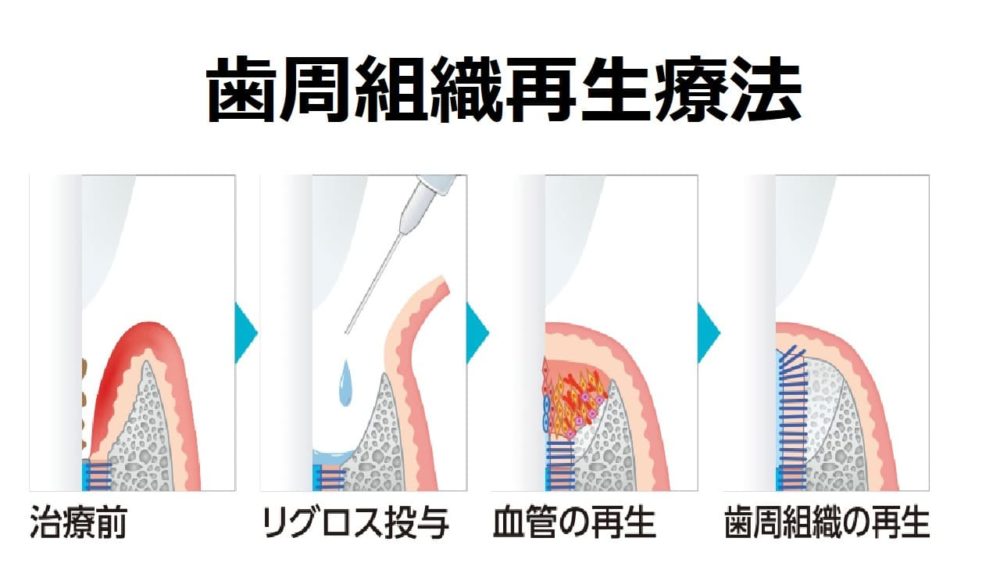
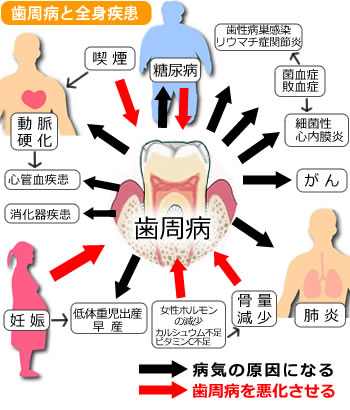


2.jpg)
3.jpg)